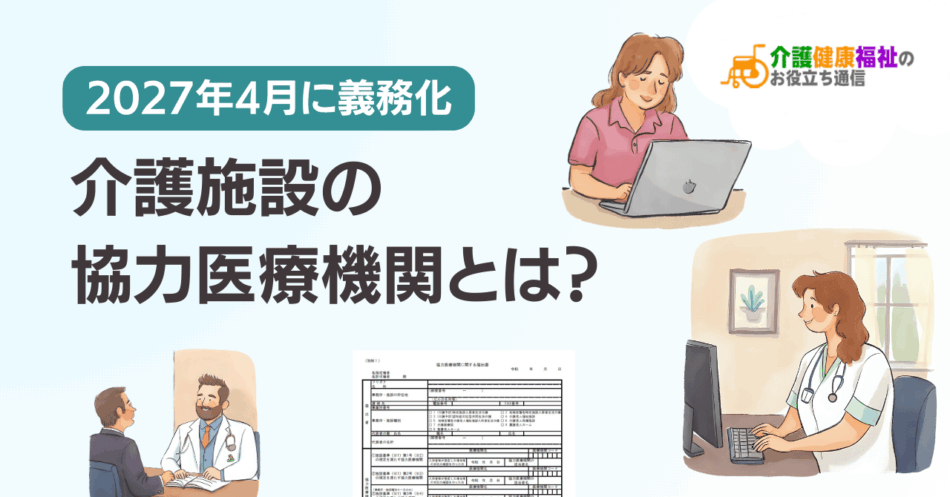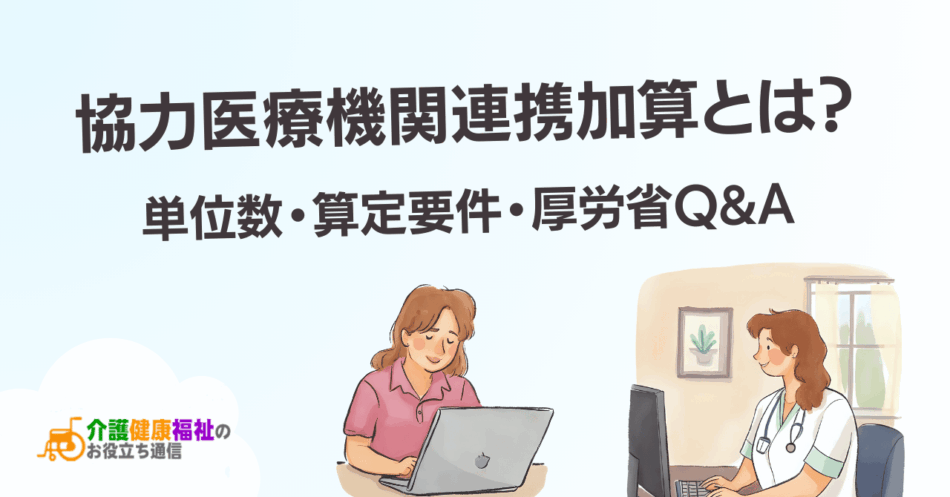
介護施設における医療連携を強化する目的で新設された「協力医療機関連携加算」。入所者の病状急変に備え、協力医療機関との間で定期的に情報共有や対応確認を行う体制を評価する加算です。単位数の違いや算定要件はもちろん、厚生労働省Q&Aで示された具体的な取り扱いを理解することは、施設運営や算定実務に直結します。
本記事では、協力医療機関連携加算の単位数、算定要件、関連する基準やQ&Aを整理し、実務者が押さえておくべきポイントを解説します。
このページの目次
協力医療機関連携加算とは?
協力医療機関連携加算は、高齢者施設等と協力医療機関との実効性のある連携体制を構築する観点から、入所者の急変時等に備えた関係者間の平時からの連携を強化するため、入所者の病歴等の情報共有や急変時等における対応の確認等を行う会議を定期的に開催することを評価するものです。
協力医療機関連携加算の単位数
協力医療機関連携加算の単位数は、以下のようになっています。算定要件の詳細については後述する内容をご確認ください。
| 協力医療機関の要件1・2を満たす場合 | それ以外の場合 | |
| 特養 | 令和7年3月まで 100単位/月 令和7年4月から 50単位/月 |
5単位/月 |
| その他 | 100単位/月 | 40単位/月 |
要件1 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保
要件2 施設からの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保
加算を算定しない場合にも運営上必要な協力医療機関の条件
「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について」に記載されている協力医療機関についての文書を整理して掲載します。この内容は介護老人福祉施設の運営基準に記載されている内容なので、他の施設形態も内容は同様ですが、指定を受けて運営している施設形態ごとの運営基準をご確認ください。
(協力医療機関等)
第二十八条 指定介護老人福祉施設は、入所者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、次の各号に掲げる要件を満たす協力医療機関(第三号の要件を満たす協力医療機関にあっては、病院に限る。)を定めておかなければならない。ただし、複数の医療機関を協力医療機関として定めることにより当該各号の要件を満たすこととしても差し支えない。
一 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保していること。
二 当該指定介護老人福祉施設からの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。
三 入所者の病状が急変した場合等において、当該指定介護老人福祉施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。
2 指定介護老人福祉施設は、一年に一回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、当該指定介護老人福祉施設に係る指定を行った都道府県知事(指定都市及び中核市にあっては、指定都市又は中核市の市長)に届け出なければならない。
3 指定介護老人福祉施設は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第十七項に規定する第二種協定指定医療機関(次項において「第二種協定指定医療機関」という。)との間で、新興感染症(同条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第八項に規定する指定感染症又は同条第九項に規定する新感染症をいう。次項において同じ。)の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。
4 指定介護老人福祉施設は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。
5 指定介護老人福祉施設は、入所者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に、当該入所者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び当該指定介護老人福祉施設に速やかに入所させることができるように努めなければならない。
6 指定介護老人福祉施設は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。
基準省令第 28 条は、指定介護老人福祉施設の入所者の病状の急変時等に 対応するための協力医療機関をあらかじめ定めておくこと、新興感染症の診療等を行う医療機関と新興感染症発生時等における対応を取り決めるよう努めること、歯科医療の確保の観点からあらかじめ協力歯科医療機関を定めておくよう努めること等を規定したものであること。 協力医療機関及び協力歯科医療機関は、指定介護老人福祉施設から近距離にあることが望ましい。
協力医療機関等の基本
- 介護老人福祉施設は、入所者の急変時等に対応するため協力医療機関をあらかじめ定めること。
- また、新興感染症に対応する医療機関との取決めや、歯科医療の確保の観点から協力歯科医療機関を定めるよう努めること。
- 協力医療機関・協力歯科医療機関は施設から近距離にあることが望ましい。
協力医療機関との連携(第1項)
- 急変時の相談・診療体制を常時確保し、緊急時に原則入院可能な協力病院を定める。
- 複数の医療機関を組み合わせて要件を満たすことも可能。
- 在宅療養支援病院・診療所、地域包括ケア病棟(200床未満)、在宅療養後方支援病院等との連携が想定される。
- 専用病床を常に確保する必要はなく、地域全体で在宅療養者を受け入れる体制があればよい。
- 義務化にあたり、2027年3月31日まで経過措置として努力義務、同年4月から完全義務化。
連携体制の届出(第2項)
- 実効性確保のため、年1回以上、急変時対応を協力医療機関と確認し、その内容・名称を指定権者(都道府県知事、指定都市・中核市市長)に届け出ること。
- 名称・契約内容変更があれば速やかに届出。
- 経過措置期間中に要件を満たす医療機関を確保できていない場合は、確保計画を併せて届け出ること。
新興感染症対応(第3項)
- 入所者が新興感染症に感染した場合に備え、第二種協定指定医療機関と平時から対応を取り決めるよう努めること。
- 内容は相談・診療・入院要否判断・入院調整等。
- 薬局や訪問看護ステーション等との連携も妨げられない。
協力医療機関が第二種協定指定医療機関の場合(第4項)
- 通常の急変時対応確認と合わせ、新興感染症発生時の対応についても協議を行うこと。
- 取り決めが成立しない場合もあるが、日常的に連携のある協力医療機関と合意形成を行うことが望ましい。
入院後の再入所(第5項)
- 「速やかに入所させるよう努める」とは、常時ベッドを確保することを意味せず、退院後の再入所をできる限り円滑に行うことを求めるものである。
協力医療機関連携加算を算定しない場合にも運営上必要な協力医療機関についての詳しい条件や役割は以下の記事で紹介しています。
施設種別ごとの協力医療機関義務化対象一覧
| 施設種別 | 2027年4月以降の位置付け | 2027年3月末までの位置付け |
|---|---|---|
| 介護老人保健施設 | 義務 | すでに義務 |
| 特別養護老人ホーム | 義務 | 努力義務 |
| 地域密着型特養 | 義務 | 努力義務 |
| 介護医療院 | 義務 | 努力義務 |
| 養護老人ホーム | 義務 | 努力義務 |
| 軽費老人ホーム | 義務 | 努力義務 |
| 特定施設入居者生活介護 | 義務 | 努力義務(2024年改定で追加) |
| 地域密着型特定施設 | 義務 | 努力義務 |
| 認知症対応型共同生活介護(グループホーム) | 義務 | 努力義務 |
協力医療機関連携加算の算定要件
協力医療機関連携加算の概要
①協力医療機関連携加算は、高齢者施設等と協力医療機関との実効性のある連携体制を構築する観点から、入所者の急変時等に備えた関係者間の平時からの連携を強化するため、入所者の病歴等の情報共有や急変時等における対応の確認等を行う会議を定期的に開催することを評価するものである。
入所者の病歴等の情報共有や急変時等における対応の確認等を行う会議
②会議では、特に協力医療機関に対して診療の求めを行うこととなる可能性が高い入所者や新規入所者を中心に情報共有や対応の確認等を行うこととし、毎回の会議において必ずしも入所者全員について詳細な病状等を共有しないこととしても差し支えない。
単位数
③ 協力医療機関が指定介護老人福祉施設基準第 28 条第1項第1号から第3号までに規定する要件(以下、3要件という。)を満たしている場合には⑴の 50 単位(令和7年3月 31 日までの間は 100 単位)、それ以外の場合は⑵の5単位を加算する。⑴について、複数の医療機関を協力医療機関として定めることにより3要件を満たす場合には、それぞれの医療機関と会議を行う必要がある。⑴を算定する場合において、指定介護老人福祉施設基準第 28 条第2項に規定する届出として3要件を満たす医療機関の情報を都道府県等に届け出ていない場合には、速やかに届け出ること。
(協力医療機関等)
第二十八条 指定介護老人福祉施設は、入所者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、次の各号に掲げる要件を満たす協力医療機関(第三号の要件を満たす協力医療機関にあっては、病院に限る。)を定めておかなければならない。ただし、複数の医療機関を協力医療機関として定めることにより当該各号の要件を満たすこととしても差し支えない。
一 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保していること。
二 当該指定介護老人福祉施設からの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。
三 入所者の病状が急変した場合等において、当該指定介護老人福祉施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。
概ね月に1回以上会議を定期的に開催
④ 「会議を定期的に開催」とは、概ね月に1回以上開催されている必要がある。ただし、電子的システムにより当該協力医療機関において、当該施設の入所者の情報が随時確認できる体制が確保されている場合には、定期的に年3回以上開催することで差し支えないこととする。なお、協力医療機関へ診療の求めを行う可能性の高い入所者がいる場合においては、より高い頻度で情報共有等を行う会議を実施することが望ましい。
会議でのテレビ電話装置等の活用
⑤ 会議は、テレビ電話装置等(リアルタイムでの画像を介したコミュニケーションが可能な機器をいう。以下同じ。)を活用して行うことができるものとする。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。
会議は入所者の病状が急変した場合の対応の確認と一体的に行うことも可能
⑥ 本加算における会議は、指定介護老人福祉施設基準第 28 条第2項に規定する、入所者の病状が急変した場合の対応の確認と一体的に行うこととしても差し支えない。
会議の開催の記録
⑦ 会議の開催状況については、その概要を記録しなければならない。
協力医療機関連携加算に関する厚生労働省 Q&A
職種は問わないが、入所者の病歴その他健康に関する情報を協力医療機関の担当者に説明でき、急変時等における当該協力医療機関との対応を確認できる者が出席すること。
要支援者については、「介護予防認知症対応型共同生活介護費」の対象となるが、これについては、協力医療機関連携加算は設けていないことから、算定できない。
本加算制度は協力医療機関と利用者の現病歴等の情報共有を行う会議を定期的に開催することを評価するものである。ショートステイ等既に居宅サービスを利用している者の情報共有は居宅サービスのケアマネジャー等が行うものであるため、当該加算の対象とはならない。
差し支えない。
例えば、都道府県が構築する地域医療介護総合確保基金の「ICTを活用した地域医療ネットワーク基盤の整備」事業を活用した、地域医療情報連携ネットワーク(以下「地連NW」という。)に参加し、当該介護保険施設等の医師等が記録した当該介護保険施設等の入所者の診療情報及び急変時の対応方針等の情報について当該地連NWにアクセスして確認可能な場合が該当する。
この場合、当該介護保険施設等の医師等が、介護保険施設等の入所者の診療情報及び急変時の対応方針等についてそれぞれの患者について1ヶ月に1回以上記録すること。
なお、入所者の状況等に変化がない場合は記録を省略しても差し支えないが、その旨を文書等により介護保険施設等から協力医療機関に、少なくとも月1回の頻度で提供すること。
協力医療機関連携加算は、高齢者施設等と協力医療機関との実効性のある連携体制を構築することを目的とした体制加算であり、入所者全員について算定されるもの。なお、協力医療機関に対して病歴等の情報を共有することについて同意が得られない入所者であっても、当該入所者の急変時等において協力医療機関による診療等が受けられるよう取り組むことが必要。
まとめ
協力医療機関連携加算は、介護施設と協力医療機関との連携体制を評価する加算であり、単位数の違いは協力医療機関が基準要件を満たしているかどうかで決まります。算定には、入所者の病歴や急変時対応について定期的に会議を行うことが求められ、会議の頻度や方法についても厚生労働省のQ&Aで具体的に示されています。
また、加算を算定しない場合でも、介護施設は基準省令に基づき協力医療機関を定め、急変時や入院対応の体制を整えておく義務があります。今後は協力医療機関の義務化や感染症対応なども含め、医療と介護の連携はさらに重視される流れです。
実務においては、協力医療機関との契約や届出を適切に行い、日常的な情報共有を確実に積み重ねることが、加算算定だけでなく入所者の安心と安全を守るために欠かせない取り組みとなります。
2024年4月・6月介護報酬改定の情報
令和6年~8年 地域区分(介護)区市町村の等級一覧(2024年4月~)
介護保険区分支給限度基準額一覧(要支援・要介護)
2024年介護報酬改定後の介護保険サービスごとの介護報酬・単位数
令和6年度介護報酬改定では、4月に変更となる内容と、6月に変更になる内容があります。例えば、訪問介護費の場合、基本報酬部分は4月から、処遇改善加算等は6月から変更という2段階での変更が生じることがあります。詳細は各記事に添付している厚生労働省のサイトからご確認ください。
介護保険の居宅サービス介護給付費単位数(対象:要介護)
- 居宅介護支援費 2024年4月からの介護報酬・単位数一覧
- 訪問介護費 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
- 訪問看護費 2024年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 訪問リハビリテーション費 2024年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 通所介護費(デイサービス) 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
- 通所リハビリテーション費(デイケア) 2024年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 短期入所生活介護費(ショートステイ) 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
- 居宅療養管理指導費 2024年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 福祉用具貸与費 2024年4月からの介護報酬・単位数一覧
地域密着型サービスの単位数改定内容
- 地域密着型通所介護費(小規模デイサービス) 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
- 認知症対応型共同生活介護費(認知症グループホーム) 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
- 小規模多機能型居宅介護費(認知症グループホーム) 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
介護予防サービス(対象・要支援)
- 介護予防支援費 2024年4月からの介護報酬・単位数一覧
- 介護予防訪問看護費 2024年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 介護予防居宅療養管理指導費 2024年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 介護予防短期入所生活介護費(要支援のショートステイ) 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
- 介護予防訪問リハビリテーション費 2024年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 介護予防通所リハビリテーション費 2024年6月からの介護報酬・単位数一覧
介護予防・日常生活支援総合事業費(要支援・事業対象者)の改定内容
施設サービス等介護給付費単位数の改定内容
- 介護福祉施設サービス費(特別養護老人ホーム) 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
- 介護保健施設サービス費(介護老人保健施設:老健) 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
- 介護医療院費 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
- 特定施設入居者生活介護費(介護付き有料老人ホームなど) 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
2024年(令和6年)介護報酬改定で特徴的な加算・制度
- 介護施設の協力医療機関とは?【2027年4月に義務化】
- 協力医療機関連携加算とは?単位数・算定要件・厚労省Q&A
- 高齢者虐待防止措置未実施減算の算定要件・対象・単位・厚労省Q&A
- 居宅介護支援の「特定事業所加算」算定要件
- 生産性向上推進体制加算の算定要件
- 個別機能訓練加算(Ⅰ)サービス種別ごとの単位数・算定要件【2024/2025年】
- 認知症チームケア推進加算の算定要件 必要資格や研修を解説!
- 2024年(令和6年)6月からの「介護職員処遇改善加算」
- 2024年~ 居宅ケアマネのオンラインモニタリングの条件・要件
- 認知症介護基礎研修 eラーニングの内容・2024年義務化の対象者などを解説!
- 2025年から経営情報報告義務「介護事業財務情報データベースシステム」とは?
利用者負担軽減の仕組みの改定
補足給付(負担限度額認定)に関わる見直しは、以下のとおりです。
令和6年8月1日施行 基準費用額の見直し
令和7年8月1日施行 多床室の室料負担