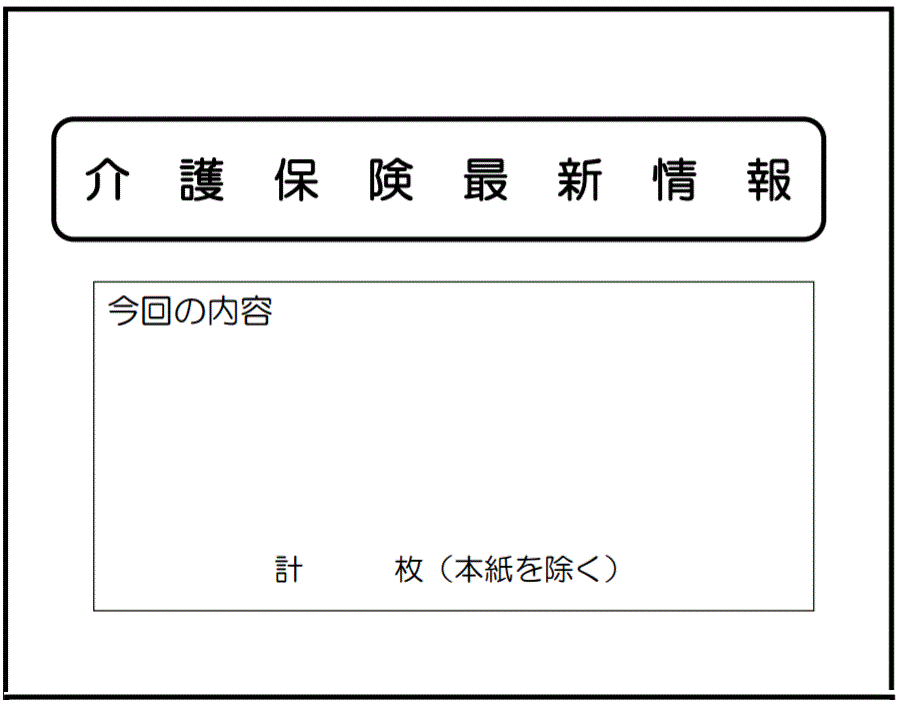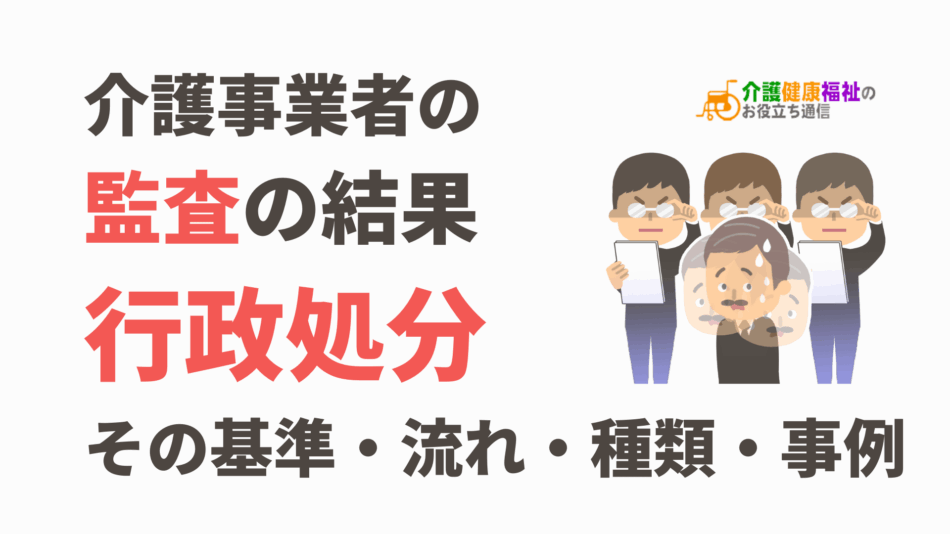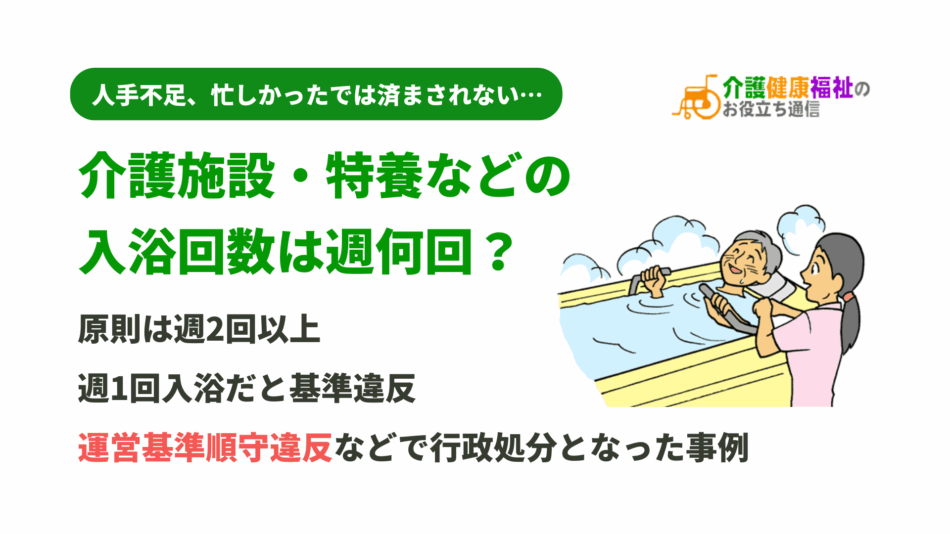
介護施設における「入浴」は、単なる清潔保持にとどまらず、皮膚疾患の予防、循環・呼吸機能の安定、睡眠や食欲の改善、そして尊厳維持に直結する重要なケアです。しかし、現実的には介護業界では慢性的な人手不足などの問題から入浴頻度が揺らぎがちです。
介護施設や老人ホーム、ショートステイなどの介護保険サービスには明確な法令基準が定められており、利用者の入浴回数が不足して週1回となる運用は原則として違反に当たり、高齢者虐待(介護・世話の放棄・放任)や人格尊重義務違反として行政処分となるケースも出ています。
この記事では、特別養護老人ホーム(特養)、短期入所生活介護(ショートステイ)、介護老人保健施設(老健)、有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護)それぞれの入浴回数の根拠条文を示し、違反事例の行政処分と運営上のポイントを整理します。
このページの目次
施設類型ごとの入浴回数と根拠条文
介護保険施設・介護保険サービスの入浴回数については「人員、設備及び運営に関する基準(通称:運営基準)」で制度上の「最低ライン」が定められています。いずれも医学的・衛生的理由で入浴が適切でない場合(感染症流行時や傷や炎症の保護等)は清拭等で代替できますが、原則として入浴回数は週2回以上が要求されています。
| 施設・サービス | 基準・条文 | 要求水準(抜粋・要旨) |
|---|---|---|
| 特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設) | 「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」第13条第2項 | 「指定介護老人福祉施設は、一週間に二回以上、適切な方法により、入所者を入浴させ、又は清しきしなければならない。」 |
| 短期入所生活介護(ショートステイ) | 「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」第130条第2項 | 「指定短期入所生活介護事業者は、一週間に二回以上、適切な方法により、利用者を入浴させ、又は清しきしなければならない。」 |
| 介護老人保健施設(老健) | 「介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準」第17条(介護) | 「介護老人保健施設は、一週間に二回以上、適切な方法により、入所者を入浴させ、又は清しきしなければならない。」
「入所者の清潔を保つため、入浴又は清拭については、一週間に二回以上行うこと。」(老人保健施設の施設及び設備、人員並びに運営に関する基準の施行について) |
| 有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護) | 「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」第185条第2項 | 「指定特定施設入居者生活介護事業者は、自ら入浴が困難な利用者について、一週間に二回以上、適切な方法により、入浴させ、又は清しきしなければならない。」 |
いずれの条文でも「入浴または清拭」を適切に実施することが求められています。したがって、定常運用としての「週1回入浴」は、医師の指示等による例外的なケースを除き、基準違反になり得ます。
運営指導と監査
運営指導とは
運営指導(実地指導)とは、介護保険事業者として指定を受けている事業者に対して、都道府県や市区町村などの担当者が介護保険サービス事業所へ出向き、適正な事業運営が行われているか確認することです。
監査とは
監査とは、介護保険法に基づくサービス提供や各自治体条例などの関係法令などで定める、各対象サービスの取扱いや給付費用の請求などのに関する事項について、不正や著しい不当が疑われる場合に、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を採ることを目的として実施されるものです。
入浴が週1回以下だったことが問題となった行政処分の実例
直近でも、入浴頻度を下げた運用に対して、自治体が厳正に行政処分を行っています。
こちらの記事では、介護事業者の監査の結果、行政処分になる流れや事例について詳しく解説しています。
千葉県船橋市の短期入所生活介護事業所で入浴が週1回、新規利用者受け入れ停止(3か月)と介護報酬3割減の行政処分
千葉県船橋市では、短期入所生活介護事業所において「8か月で延べ568回の入浴不足(実人数47人)」が確認され、高齢者虐待や人格尊重義務違反等を理由に新規利用者受け入れ停止(3か月)と介護報酬3割減の行政処分が科されています。自治体は、ショートステイの入浴は週2回以上と明記し、満床維持を優先して不足を解消しなかった点を重くみています。
参考:介護保険事業者の行政処分について、令和7(2025)年10月8日(水曜日)、千葉県船橋市指導監査課 指導監査第二係
兵庫県神戸市の指定介護老人福祉施設で4週間入浴記録がないなどで12カ月間の事業停止、補助金返還
神戸市でも、特養において長期にわたり入浴が週2回未満であった事案などを受け、運営基準遵守違反・人格尊重義務違反として処分を発出しています。地元紙は「2週間に1回程度の時期があった」旨も報じています。
参考:指定介護老人福祉施設等に対する処分及び社会福祉法人に対する勧告 、神戸市、記者発表資料(令和3年1月12日)
実務で問われる「週2回以上」の運用設計
介護保険法に関する運営基準の条文にある「一週間に二回以上」は、機械的な一律実施を求めるものではありません。厚労省の解釈通知でも、入浴は清潔保持だけでなく精神的快適さにも資することが強調され、利用者の意向や個浴など多様な手段で入浴機会を確保する趣旨が示されています。体調や創傷管理により短期的に清拭へ切り替える場合でも、個別計画への記載、リスク・便益評価、家族説明、代替ケアの記録が欠かせません。
6 介護
(3) 基準第三十七条第三項は、入浴が、単に身体の清潔を維持するだけでなく、入居者が精神的に快適な生活を営む上でも重要なものであることから、こうした観点に照らして「適切な方法により」これを行うこととするとともに、同様の観点から、一律の入浴回数を設けるのではなく、個浴の実施など入居者の意向に応じることができるだけの入浴機会を設けなければならないことを規定したものである。
老健では、併設施設と浴室を共用する場合でも、老健入所者が週二回以上入浴できる計画が条件となるなど、構造設計面でも頻度確保が前提です。
第三 施設及び設備に関する事項
カ 浴室
入浴に全面的な介助を必要とする者に必要な特別浴室については、その出入りに当たってストレッチャー等の移動に支障を生じないよう構造設備上配慮すること。~
(エ) 浴室の共用
利用計画により、併設施設の入所者等の入浴に加え、老人保健施設の入所者が週二回以上入浴できる場合に限り認められるものであること。
入浴回数に関する基準違反と監査対策のポイント
入浴頻度の未達は、しばしば人員配置の逼迫や稼働設計、介護記録の方法や認識の歪みの表れです。
勤務体制や記録整備、ケアプラン連動、感染対策といった運営基準のハードルを下げないまま満床を続けると、既存職員で介護できるキャパをオーバーして、入浴回数が減らされるなどの基準違反もやむなしという雰囲気になり、基準違反や記録の改ざんなどが常態化しやすくなります。
監査では、日々の提供記録、ケアプラン整合性、代替清拭の医学的妥当性、利用者・家族への説明履歴が詳細に確認されます。入浴ができない期間が連続する場合には、短期是正計画を作成し、受入れ調整を含めてサービス体制を戻す意思決定が必要です。
週1回入浴にとどめると何が起きるか
入浴回数が週1回になることはただ単に基準違反であるというだけでなく、利用者や働く職員にとっても過酷な状況となります。
皮膚トラブルや褥瘡リスクの上昇、便秘や睡眠障害の悪化、ADL・QOLの低下、そして「匂い」や「不快感」が生じます。入浴できない利用者が直接的な不利益者となりますが、それと同時に入浴させてもらえないという訴えを聞き、不衛生や臭う状態を見て見ぬふりしなければならない介護職員も辛い状況になります。
入浴出来ない状態では、高齢者では、皮脂膜や体温調節、創部管理への影響が顕著で、感染症やせん妄の誘因にもなり得ます。このような利用者の状態の悪化は介護計画の目標達成度やアウトカム評価にも波及しますし、最終的には報酬減算・返還や加算の算定不可といった経営上のダメージに繋がります。神戸市の公表資料や各地の処分例が示すとおり、入浴頻度の恒常的未達は人格尊重義務違反にまで評価が及ぶことがあります。
まとめ
週2回以上という基準は、施設規模や人員構成にかかわらず守るべき最低水準です。人手不足や感染期の運営は確かに難題ですが、入浴計画の前倒しや可搬浴槽・機械浴の活用、夜間帯の安全な分散運用、清拭の質向上、外部資源の一時活用など、選択肢は多様です。やむを得ず入浴機会が減る局面でも、「個別計画」「代替ケアの質」「説明と同意」「短期の是正」がそろわない限り、週1回体制は法令違反のリスクから逃れられません。
結論として、特養・ショート・老健・特定施設のいずれでも「週1回入浴」は原則として基準違反です。施設は、入浴をサービスの周縁ではなく、「生活と尊厳の中核」と位置づけ、計画・体制・記録・説明の4点を同時に満たす運営に徹することが求められます。