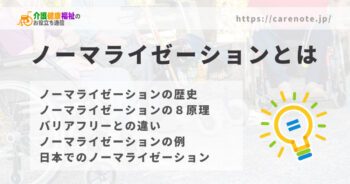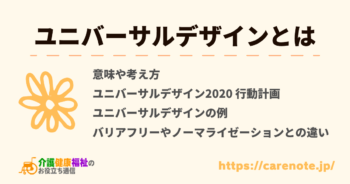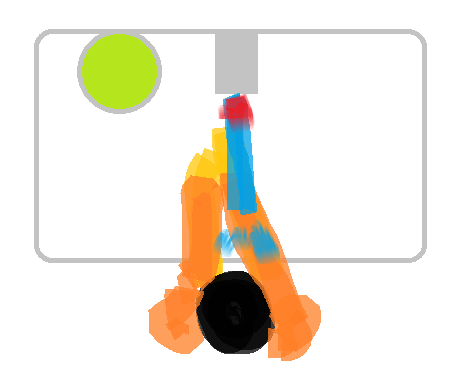自立支援などに取り組むなかで、
このページの目次
バリアフリーな設計は社会で充実、誰でも実用的な状態になってきている
センサーで自動で水が出る、簡単に動かせる蛇口
バリアフリーな水道でも袖が濡れる水流の角度だと利用する障壁になる
多目的トイレはとても便利になってきており、大人から子供までおむつを取り替えたり、汚物を処理できたり、着替えできたり、幼児のためのお丸(補助便座)があったりと、いろいろなケースを想定して排泄などができるようになりました。その中でちょこっとだけ残念だったのが洗面台なのです。洗面台は手を洗うときに使いたい設備で、車椅子の方や幼児などのバリアフリーに配慮して低い位置に設置するなど工夫されています。洗面台の下にも車椅子が入り込めるような空間を用意しているなど、かなり実用的な設計だなぁと感じるのですが、水道の水の向きがもったいない!洗面台の水受けが低い位置にあるので、車椅子の方や幼児でも水道まで届くのですが、低い位置から手を伸ばすと水が手の袖にかかってしまったり、幼児の高さだと水が跳ねて顔にかかったりしてしまうのです。
センサーで自動で水道が出ることによる弊害
幼児だけでなく、高齢者や障害者も、洗面台の縁を支点にして体を支えて水道で手を洗うというケースが結構あります。その時、どうしても自動のセンサーが動いてしまい、意図しない場所に水がかかってしまうことがあります。例えば、左側に石鹸タンクが設置されていることが多いですが、ちょうどその石鹸タンクに手を伸ばそうとすると、右側にある水の出口のセンサーが反応して水が出てきていしまい袖がびちゃびちゃに濡れてしまったりします。
すべての人にとって快適な形(ユニバーサルデザイン)はかなり難しいのですが、いろいろな気付きが合わさって少しずつ快適度が上がっていけばと思います。
介護の転職に役立つ記事
ケアマネジャーの転職は、ケアマネ専門の転職サイトを利用しよう
ケアマネジャーの転職はケアマネ専門の転職サイトの利用が安心です。自分で求人を探したり、人づてに紹介してもらったりする場合、本心では希望している条件をいろいろ我慢してしまいがちになります。転職サイトを挟むことで、希望に合う職場を見つけてもらい、見学・面接対策・条件調整なども行ってもらえるので、希望理由や面接対策で悩んだりすることも減ります。新人ケアマネも、ベテランのケアマネも専門の転職サイトの方がケアマネの求人情報を多く持っています。
居宅介護支援事業所では人手不足状態、ケアマネージャー、主任ケアマネージャー資格を有する人の求人が増えています。多くの転職サイトは介護の仕事のおまけのような感じでケアマネの転職支援をしていますが、ケア求人PECORIだけはケアマネ専門なので、登録して電話面談するときにもケアマネとしての状況や今後の働き方、賃金の相場などを相談しやすいです。
「ケア求人PECOLI」は、ケアマネージャー専門の転職サイトという大変珍しいサービスで、ケアマネに特化して全国の転職支援を行っています。他の転職サイトに登録しても、よい求人が見つからなかったり、電話の人と話が合わなかったりしてうまくいかなかったケアマネも、すぐ登録できるので一度登録してピッタリな求人・転職先の紹介を受けてみましょう。(運営:株式会社PECORI 職業紹介許可番号(厚生労働大臣認可):13-ユ-308091)