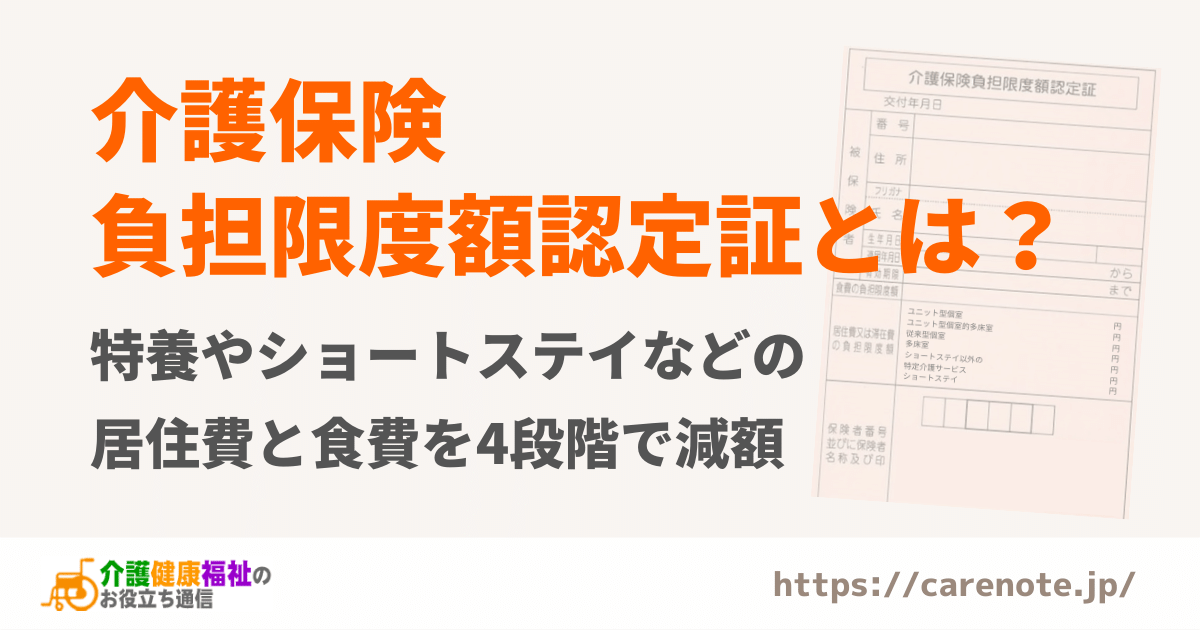ショートステイ(短期入所生活介護)は、在宅で暮らす方が短期間だけ施設に入所し、入浴や食事、機能訓練などの支援を受ける介護保険サービスです。ご本人の心身機能の維持と、ご家族の休養・就労・急な用事への対応を両立する仕組みとして位置づけられています。
この記事では、介護支援専門員の実務と、利用を検討するご本人・ご家族の判断に役立つよう、制度上の定義と役割、利用できる介護度、費用の内訳、負担限度額認定による居住費・食費の4段階減額、申し込みから契約・サービス担当者会議までの流れ、連続利用の期間(原則30日)を、表も交えてわかりやすく解説します。
このページの目次
ショートステイとは?
ショートステイは、要介護者や要支援者が短期間だけ施設に入所し、入浴や排せつ、食事などの日常生活の支援と機能訓練を受けるサービスです。ご本人の心身機能の維持とご家族の身体的・精神的負担の軽減を同時にねらう仕組みで、介護保険の居宅サービスに位置づけられています。居宅での自立した生活を支える短期入所として定義されています。
介護保険上の「短期入所生活介護」の定義と役割
介護保険法上、短期入所生活介護は、単独型の短期入所施設、介護老人保健施設、特別養護老人ホーム等に短期間入所し、施設での介護や機能訓練を通じて心身機能の維持と家族負担の軽減を図るサービスです。介護保険の制度趣旨としては「できる限り在宅での生活を続けられるようにする」ことにあり、計画的なレスパイト(介護者の休養)や在宅復帰・在宅継続の橋渡しの役割を担います。
短期入所生活介護(ショートステイ)の対象となる介護度
要介護認定で要介護1~5の方は「短期入所生活介護」を、要支援1・2の方は「介護予防短期入所生活介護」を利用できます。
いずれも、在宅生活の継続や家族の事情(病気・冠婚葬祭・出張等)に伴う一時的な支援、状態変化時の見守りや集中的支援などが想定されています。
短期入所生活介護(ショートステイ)の費用、自己負担割合と実費項目
ショートステイの費用は、介護保険が適用されるサービス費用の自己負担(原則1割、所得により2~3割)に加えて、居住費(滞在費)・食費・日常生活費などの実費が発生します。厚生労働省の解説でも、施設を利用する場合は介護サービス費の自己負担に加え、居住費・食費等の負担が必要であることが示されています。
料金構成の全体像
| 区分 | 仕組みの概要 |
|---|---|
| 介護サービス費 | 介護保険で全国統一で決められた単位×地域区分等で算出、自己負担は1~3割。 |
| 居住費(滞在費) | 1日あたりの定額。施設ごとに部屋のタイプで上限が異なります。 |
| 食費 | 提供分を日額で負担。 |
| 日常生活費等 | 日用品・レクリエーション等は実費。 |
「介護保険負担限度額認定」を受けた場合の減額(4段階)
所得や預貯金等の要件を満たし介護保険負担限度額認定を受けると、短期入所における居住費(滞在費)と食費が段階(第1~第3②、一般の第4)に応じて上限額まで減額されます。自治体の案内では、短期入所の部屋タイプごとに1日あたりの上限額が示され、申請により「認定証」が交付されます。居住費の部分は基準はあるものの各施設がある程度自由に設定できる費用であるため、負担限度なしだと高額になる場合もあります。限度額認定を受けると、その言葉の通り限度以上は自分で支払わず公的な補助となるので認定対象になるかは市区町村に問い合わせて方が良いでしょう。
| 負担段階の考え方(概要) | 短期入所に適用される上限の考え方 |
|---|---|
| 第1~第3段階(非課税世帯等) | 居住費・食費に全国統一の上限額が設定され、市町村が認定・適用。 |
| 第4段階(課税世帯等) | 原則として減額の上限は適用されません。 |
介護保険負担限度額の対象となる施設
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設
- 介護医療院
- 介護療養型医療施設
- 短期入所生活介護(ショートステイ)
- 短期入所療養介護
介護保険負担限度額認定について詳しくは「介護保険負担限度額認定証とは 居住費と食費を4段階で減額」の記事で説明しています。
ショートステイの利用希望から利用開始までの流れ
まずは居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)、要支援の方は地域包括支援センターに相談し、アセスメントとケアプラン原案の作成を行います。続いてサービス担当者会議で目標や支援内容、期間、医療情報や服薬、持参物、送迎の要否などをすり合わせ、受け入れ可能な事業所と契約を結びます。
日程が決まったら、入所中の過ごし方や緊急時の連絡手順を確認し、ショートステイの職員が状態や希望などを確認の上、滞在中のケアの計画を説明し利用開始となります。
ショートステイどのくらいの期間連続して利用できるか
ショートステイの連続利用は原則30日までが報酬算定の対象です。長期の連続入所が施設入所と実質的に同じ状態になることを防ぐ趣旨によるもので、やむを得ない事情で30日を超える必要がある場合は、保険者が示す取扱い(リセット条件や減算適用など)に沿って運用されます。
自治体の周知資料でも、31日目以降の取扱いに関する注意や、同一事業所での長期利用時の減算等に関する留意が示されています。具体的な判断は保険者(市区町村)の取扱いに従ってください。長期の利用になりそうな場合には、早めに市区町村に問い合わせして対応方法を確認しておきましょう。
まとめ
ショートステイは、在宅生活の継続を支える重要な支援であり、要介護の方は短期入所生活介護、要支援の方は介護予防短期入所生活介護として利用できます。費用は、介護サービス費の自己負担に居住費・食費などが加わる設計で、負担限度額認定により食費・居住費の4段階の減額が受けられる場合があります。
連続利用は原則30日までで、超える場合の扱いは保険者の取扱いに従います。ご本人とご家族の状況に合わせ、ケアマネジャーと計画的に日程を組み、目的と必要な支援内容をはっきりさせることが、安心で納得感のある利用につながります。