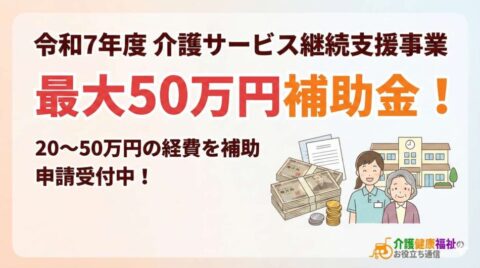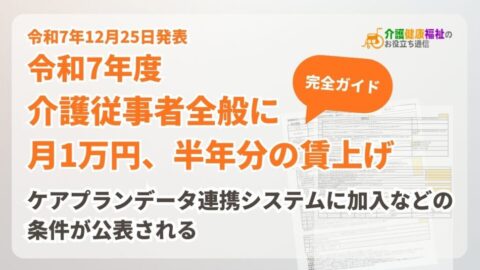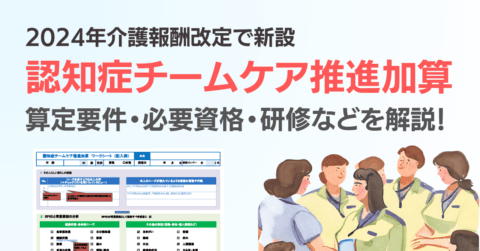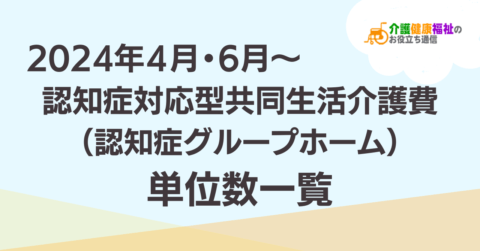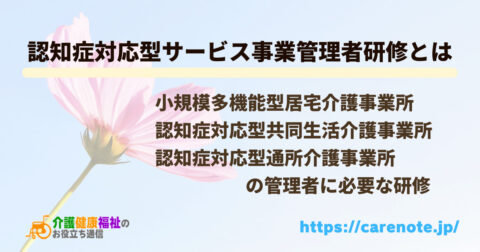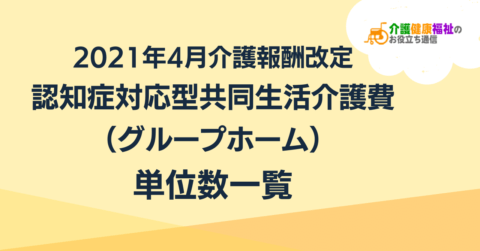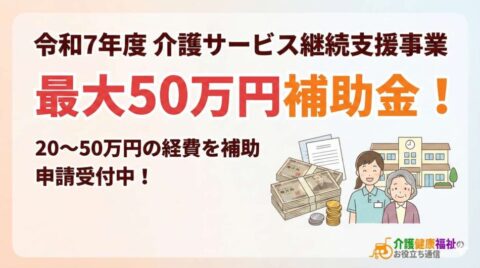
厚生労働省は2026年1月14日に、「介護保険最新情報 Vol.1461(介護事業所等及び介護施設等に対するサービス継続支援事業に関する交付要綱及び実施要綱等について)」という事務連絡で補正予算として組み込んだ...
日本の介護保険制度にある認知症対応型共同生活介護とは、認知症を持つ高齢者が少人数で共同生活を送るための介護サービスです。一般的に「グループホーム」とも呼ばれ、認知症の進行を遅らせ、生活の質を向上させることを目的としています。このサービスでは、認知症の高齢者がスタッフのサポートを受けながら、家庭的な環境で自立した生活を営むことができるように支援します。日常生活の援助や機能訓練、レクリエーション活動が提供され、利用者が安心して過ごせるように工夫されています。また、少人数のユニットケアを採用することで、一人ひとりに合わせたきめ細やかなケアが可能です。認知症対応型共同生活介護は、地域社会とのつながりを大切にし、利用者が地域の一員として活動に参加できるように支援します。これにより、認知症の高齢者が孤立せず、社会との関わりを持ちながら生活を続けることができます。