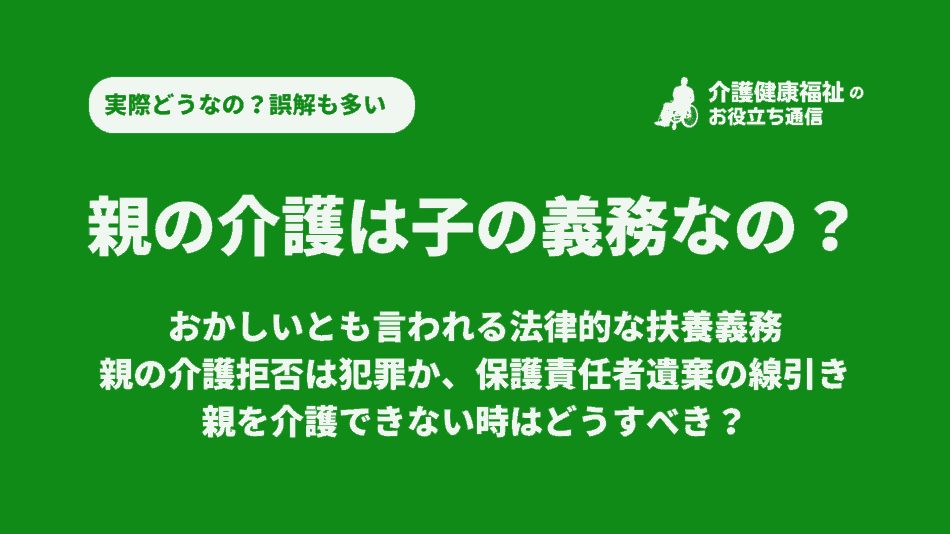
親の介護をめぐる気持ちは、愛情と疲労、義務感と反発が入り混じります。
子どもの世話をするのは親の義務だと言われれば、それはそうだと納得がいきますが、親の介護も子や孫の義務だと言われると、そうなのだけど、いろいろな親子関係がある中で義務だと言われるとそれっておかしいんじゃない?と気持ちを抱く人も多くいます。
介護職やケアマネは、家族からの「もう無理です」「あんな親、見たくありません」という場面に何度も向き合い、当事者の子や孫は「自分がやるしかないのか」と自問します。
この記事は、感情を置き去りにせず、日本の法律が定める「扶養義務」と刑罰の線引きを原文とともに確認し、介護を担えないときに罪に問われず生活や仕事を守る方法をまとめます。
このページの目次
日本の法律は「親の介護」をどう定めているのか
日本の民法は、親子や兄弟姉妹に「扶養義務」があると定めています。根拠は次の条文です。
(扶養義務者)民法第877条
「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。」
「家庭裁判所は、特別の事情があるときは、……三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。」
「扶養」は、多くの場合お金や生活費の分担、介護費用の負担、必要な支援手段の手配を意味します。誰がどれだけ担うかはまず家族で話し合い、それでもまとまらないときは家庭裁判所が、当事者の資力や必要性を考えて分担や方法を決めます。
(扶養の順位)民法第878条
「扶養をする義務のある者が数人ある場合において……家庭裁判所が、これを定める。」(扶養の程度又は方法)民法第879条
「……扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。」
民法では「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。」とは言いつつも、「家で子どもが直接に介護をすること」そのものを命じてはいないという点がよく誤解されています。経済的・社会的に合理的なやり方で支える義務があるのであって、必ずしも家族が自ら身体介護を行う義務ではありません。
親の介護を拒否したら犯罪になるのか
刑事罰の観点では、単に「介護をやめたい」「施設に入ってほしい」と考えるだけで犯罪になるわけではありません。ただし、現実に保護監督の任務にある人が、要保護の高齢者を置き去りにしたり、生命・身体に危険な状態を放置した場合は、刑法の「保護責任者遺棄等」に該当し得ます。
刑法第218条(保護責任者遺棄等)
「老年者……を保護する責任のある者が、その者を遺棄し、又は保護を怠ったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。」
ここでいう「保護責任者」とは、実際に介護・監督の任務を負っている者を指します。遠方で同居していない子が直ちに処罰されるわけではありませんが、同居者や事実上の要介護者が危険を知りながら放置すれば、刑事責任が問題になります。
被害が拡大すれば、致死傷の重い罪も視野に入ります。虐待が疑われる場面では、高齢者虐待防止法に基づき、市町村への通報義務(生命・身体に重大な危険がある場合の直通報)や関係者の早期発見の努めも定められています。
親の介護はしない、それでも違法にしない着地の仕方
家族が直接に介護を続けられない場合でも、法に適った方法をとれば罪に問われることはありません。鍵は、必要な支援を怠らず、代替手段につなぐことです。次の表は、よくある状況と現実的な解決の道筋を、制度の窓口と一緒に示したものです。
| 状況 | 現実的な選択肢 | 何が「違法回避」につながるか |
|---|---|---|
| 同居介護が限界。心身が消耗している | 地域包括支援センターへの相談から、ケアマネジャーによるケアプラン作成。訪問介護・通所介護・ショートステイの組み合わせで在宅を維持する。 | 専門職につなぎ、必要な見守りと介助を外部化することで「放置」に当たらない状況を作る。 |
| 連続の在宅は困難。短期で預けたい | 介護保険の短期入所(ショートステイ)を計画的に利用する。 | 一時的でも安全が担保され、保護責任の不履行を避けられる。 |
| 長期の入所が必要 | 特養、老健、有料老人ホーム等への入居・入所を検討し、費用は家族で分担または公的負担を併用する。 | 「家での直接介護」をやめても、適切な保護措置を講じていれば違法ではない。 |
| 費用が重い | 介護保険の高額介護サービス費や補足給付(負担限度額認定)で食費・居住費の上限軽減を活用する。 | 経済的理由での放置を避ける制度的な受け皿。2024年以降の基準改定も公表されている。 |
| 認知症で契約や金銭管理が難しい | 成年後見制度を家裁に申立て、介護契約や施設入所の手続きを代理してもらう。 | 法的代理人の関与で、必要な保護措置を確実に実行できる。 (制度解説は各自治体・法テラス等) |
| 兄弟姉妹で負担の揉め事が続く | 扶養の分担や金額は家庭裁判所の調停・審判で決めてもらう。 | 「誰も払わない・決めない」状態を解消し、義務の履行方法を法的に確定する。民法878条・879条に基づく。 |
よくある誤解
ここまで説明してきたように、「親の介護をしないと逮捕される」は誤りです。
刑法が問題にするのは、保護すべき立場にありながら危険を放置した結果としての遺棄であり、「介護サービスや入所に切り替える」という合理的措置はむしろ望ましい選択です。介護保険制度の目的としても、家族に介護を押し付けるばかりでなく、社会的に要介護者を支援するという意義も含まれています。
「兄弟が多いから、長男長女が介護や費用負担をすべきで末っ子は免除」という話もたまに聞きますが、根拠がありません。
扶養義務者が複数いるときは、まず当事者で協議し、それでも決着しなければ家庭裁判所が分担や順位を定めます。民法の条文は、力関係ではなく、必要性と資力のバランスで決める仕組みになっています。
親の介護について、感情と現実の落としどころ
介護の現場では、「何とか親孝行をしなければ…」「良い子であろうとするほど壊れていく」瞬間があります。
今日できる現実的な一歩は、ケアマネがすでについている場合には親の介護が厳しいということを伝えるべきです。状況に合わせて一時的なショートステイなどを考えてくれることもありますし、もうどうにもならない状態ならば施設入所などを提案する話も出てくることでしょう。
まだ介護度がついていない場合、地域包括支援センターや市役所に問い合わせ、現状を共有することもありです。
その上で、在宅継続か施設かの方向を決め、費用が難しければ負担軽減の申請、契約が難しければ後見申立て、家族間で揉めたら調停という順番で、法と制度のレールに乗せていきます。これは「親を見捨てること」ではなく、「法が予定する保護の仕方」を選ぶことであり、罪に問われないための確かな道筋でもあります。
親の介護は義務ですが、「支え方」は選べます
民法は、親子や兄弟姉妹に相互の扶養義務を定めていますが、その中身は金銭や手配など多様で、「自宅で直接介護せよ」とは命じていません。刑事罰が問題になるのは、保護責任のある人が危険を知りつつ放置した場合です。介護を担えないときは、介護保険サービスや入所、費用の公的軽減、成年後見、家庭裁判所の関与といった代替手段を使えば、違法にせずに親を守り、自分の生活や仕事も守れます。感情の重さを否定する必要はありません。法の言葉に沿って「支え方」を選ぶことが、家族にも介護職にも、いちばん現実的でやさしい解だと考えます。
