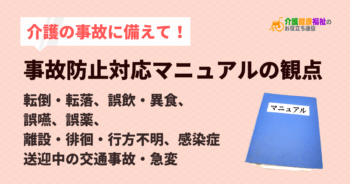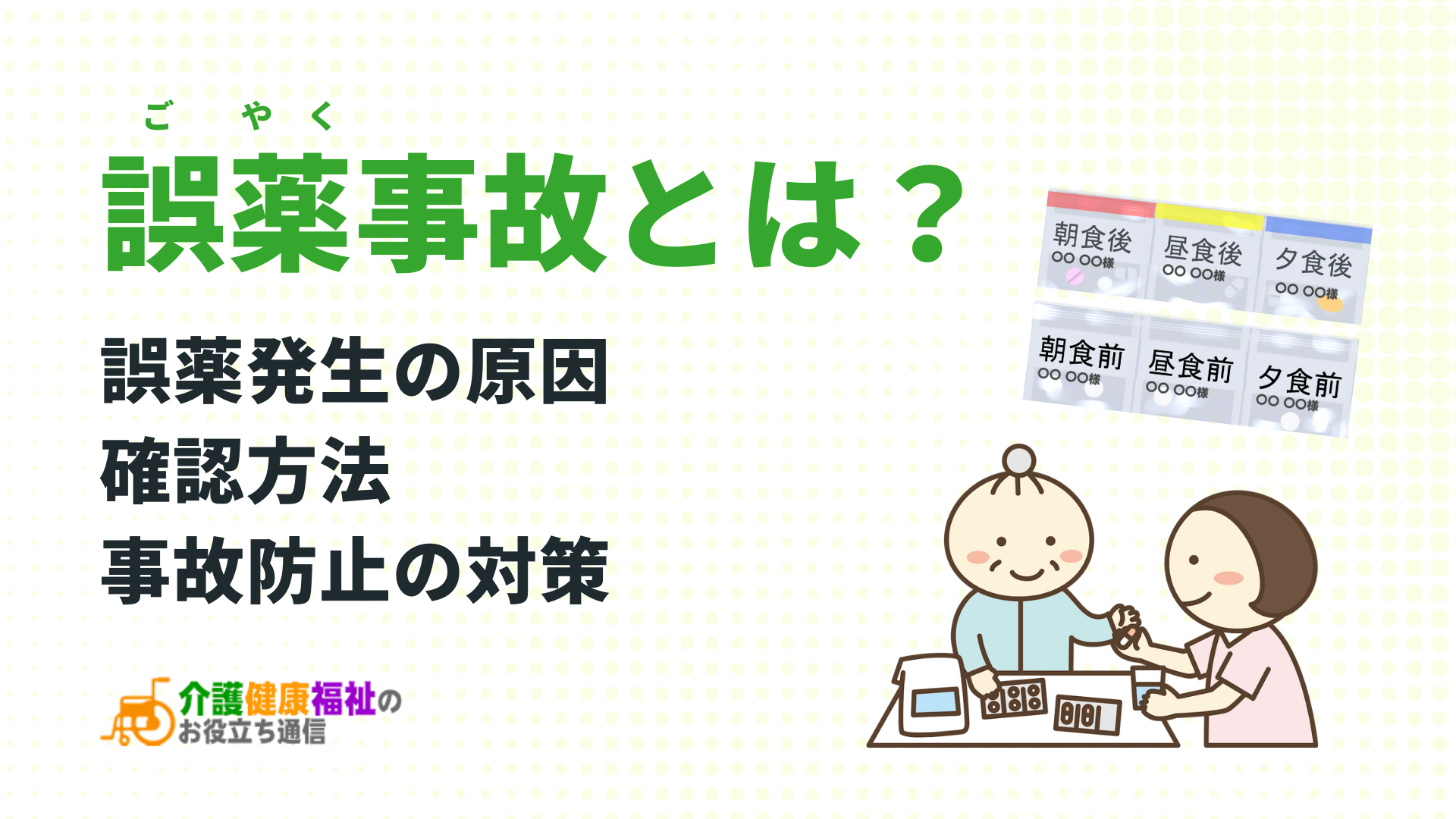
誤薬とは
誤薬とは、利用者が誤った種類、量、時間、方法で薬を飲んでしまうことです。命に関わる重大な事故であり、医療や介護業界では「ごやく」という読み方をすることが多いです。(国語辞典という言葉は介護医療業界ではよく使われる言葉ですが、一般的には通じにくい言葉です)
広告
誤薬防止のために確認すべき6R
誤薬事故を防止するための具体的な確認方法として、以下の6Rが推奨されています。この6つの確認ポイントでいずれかのミスが生じてしまった場合には誤薬事故が発生したといえます。
- 正しい患者・利用者(Right Patient)
- 正しい薬品・薬剤(Right Drug)
- 正しい目的(Right Purpose)
- 正しい用量(Right Dose)
- 正しい用法(Right Route)
- 正しい投与時間(Right Time)
広告
介護現場での誤薬事故の原因
誤薬は、薬の内容や量によっては生命に重大な危機を及ぼす可能性がある事故です。利用者が居室にいるときに転倒や転落してしまう事故などと違い、誤薬事故は施設のスタッフの思い込みやうっかり、配薬の仕組みにより、ヒューマンエラーが原因となりやすい事故です。誤薬が起こる要因として、食事時間や就寝前など複数のケアが重なってしまう状況、確認不足、配薬に関するシステムがチーム内で統一されていないなども誤薬の原因の根底にあることもあります。

広告
違う利用者に飲ませてしまう誤薬事故を防ぐための対策方法
誤薬事故で多い例として「違う利用者に薬を飲ませてしまう」というものがあります。違う利用者に薬を飲ませてしまうという誤薬事故は、施設の職員が起こしてしまうヒューマンエラーであり、起こしてはならない事故です。薬が本人のものであるか確認する、といった基本事項を職員全員で徹底することはもちろんですが、以下のように事故が起きない服薬介助の仕組みを作ることも大切です。誤薬事故が起きてしまった際には事故報告書を提出する必要がありますが、事故報告書でよく出てくる原因と対策方法は以下のような点になります。
- 薬の一包化をして氏名と飲む時間をわかるようにする(バーコードで確認するシステムなどを導入する)
- 食前薬・食後薬それぞれの配薬ボックスを用意し、薬の取り間違いや飲み忘れを防止できるようにする。
- 食後に飲む薬は配膳時に配らず、食後に配薬ボックスから取り出すようにする
- 配薬ボックスから薬を取り出すときのダブルチェック
- 配薬ボックスから薬を取り出すときは1名分だけにする
- 利用者のそばで薬袋をあけて口に入れる前のチェック
- 薬が飲み終わるまでしっかり見届ける

広告
配薬ボックスに薬を準備するときのミスの対策方法
配薬ボックスに用意する段階では、薬剤師や看護職員などが行うことが多いですが、配薬ボックスに薬を準備する段階で間違えてしまうこともあるため、事故を防ぐための対策は大切です。誤薬事故が起きてしまった際には事故報告書を提出する必要がありますが、事故報告書でよく出てくる原因と対策方法は以下のような点になります。
- 作業を中断するとエラーの原因となりやすいため、配薬と別の業務を同時進行で行わない
- 責任を明確化するためにも、この作業をした職員が誰なのかを記録しておく
- 配薬ボックスのケースには、利用者1人1人のフルネームを明記する。
- トレーの色は朝・昼・夕で色分けるなど、一目でわかりやすい工夫をする
- 薬は薬局に一包化してもらう
- 配薬ボックスの色と同じカラーラインをつけてもらう

広告
まとめ
薬を扱う際には複数回のチェックを行うことを習慣化や、誤薬を防止する業務フロー・システムを整えることが重要であり、誤薬の原因になるヒューマンエラーを減らすことにつながります。誤薬は、対応した職員に責任があると言われがちですが、職員数、職員の体調や体制、多重労働などのコンディションでもエラーは起きやすくなるので、すべてがその職員が原因というわけではなく誰でも起きてしまう可能性があるものとして一人を責めず、みんなが誤薬事故を起こしにくい体制づくりと仕組みの浸透ができることに時間や労力を注ぎましょう。
そのほかの介護事故と合わせて、事故が起きにくい仕組みづくり、事故対策を徹底していきましょう。
介護の転職に役立つ記事
ケアマネジャーの転職は、ケアマネ専門の転職サイトを利用しよう
ケアマネジャーの転職はケアマネ専門の転職サイトの利用が安心です。自分で求人を探したり、人づてに紹介してもらったりする場合、本心では希望している条件をいろいろ我慢してしまいがちになります。転職サイトを挟むことで、希望に合う職場を見つけてもらい、見学・面接対策・条件調整なども行ってもらえるので、希望理由や面接対策で悩んだりすることも減ります。新人ケアマネも、ベテランのケアマネも専門の転職サイトの方がケアマネの求人情報を多く持っています。
居宅介護支援事業所では人手不足状態、ケアマネージャー、主任ケアマネージャー資格を有する人の求人が増えています。多くの転職サイトは介護の仕事のおまけのような感じでケアマネの転職支援をしていますが、ケア求人PECORIだけはケアマネ専門なので、登録して電話面談するときにもケアマネとしての状況や今後の働き方、賃金の相場などを相談しやすいです。
「ケア求人PECOLI」は、ケアマネージャー専門の転職サイトという大変珍しいサービスで、ケアマネに特化して全国の転職支援を行っています。他の転職サイトに登録しても、よい求人が見つからなかったり、電話の人と話が合わなかったりしてうまくいかなかったケアマネも、すぐ登録できるので一度登録してピッタリな求人・転職先の紹介を受けてみましょう。(運営:株式会社PECORI 職業紹介許可番号(厚生労働大臣認可):13-ユ-308091)