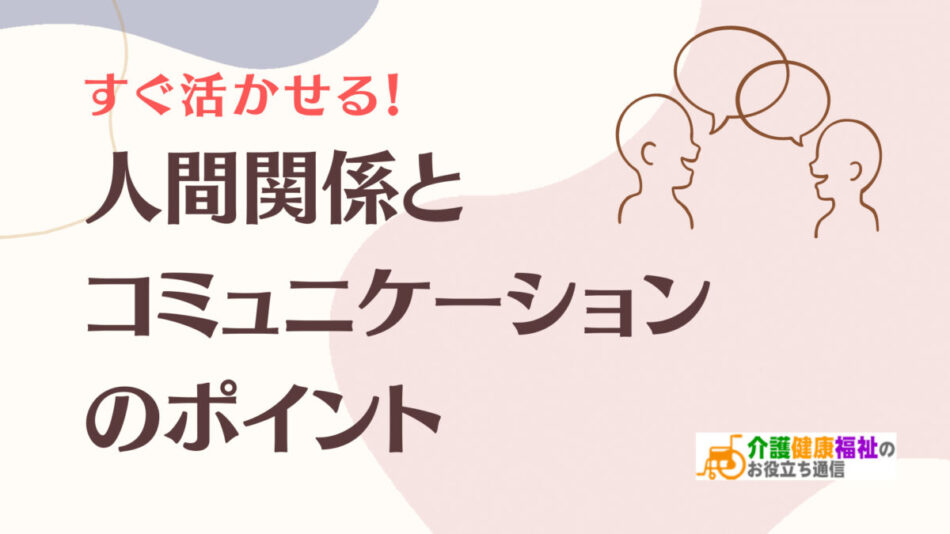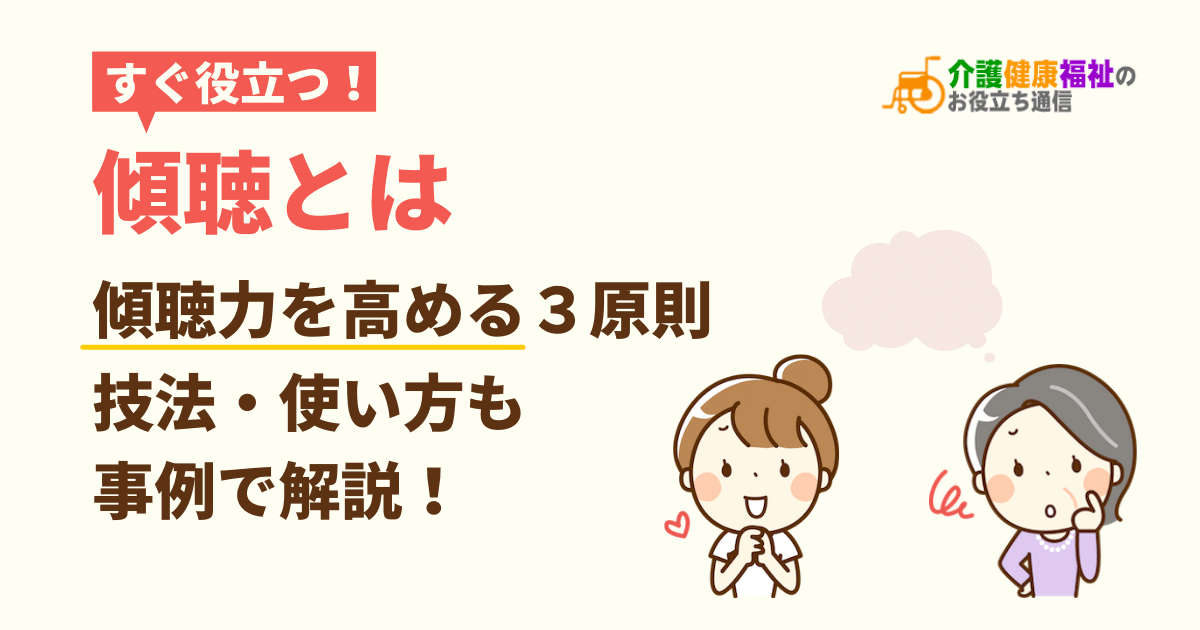
傾聴とは何か、傾聴の3原則や介護・看護での傾聴の技法・使い方を事例を交えて解説します。この記事で、傾聴・共感・受容の違いを理解し、傾聴の傾聴のポイントや、具体例を挙げて傾聴の技法や使い方、相槌や返答の仕方を紹介します。傾聴ボランティアやコミュニケーションにきっと役立つ内容になっています。
このページの目次
傾聴とは何かどう使うかについて分かりやすくまとめた動画
傾聴について動画で知りたい方はこちらをご覧ください。
傾聴とは
傾聴とは、相手に寄り添いながら話を聴くことを言います。寄り添いながら話を聴くということは相手の話に共感し受け止めることです。
傾聴の「聴」は身を入れて聞くという意味になり、ただ話を聞くだけでは傾聴ではありません。
介護において傾聴は欠かせなくてはならないものであり、傾聴を理解することによって介護のスキルを格段に向上させることができます。
傾聴力とは
傾聴力とは、「共感的理解」「無条件の肯定的関心」「自己一致」の3つの原則ができていることです。
傾聴は英語で「積極的傾聴(Active Listening)と言われており、この3つの原則はアメリカの心理学者カール・ロジャーズによって提唱されました。
傾聴力の3原則
1共感的理解
共感的理解とは、相手の考え、話し、感情をその通りだと感じ、気持ちや立場を察することです。
2無条件の肯定的関心
無条件の肯定的関心とは、相手の話を良い悪いと決めつけず、ありのままを受容することです。
3自己一致
自己一致とは、自分が感じていることと相手の感情や話すことが一致していることです。
傾聴・共感・受容の違い
上記で傾聴は相手に寄り添いながら話を聴くことと説明しましたが、共感や受容も「受け入れる」ような意味ですよね。この3つの意味合いはどのように違うのでしょうか?
| 傾聴 | 注意深く相手の話を聴く、真摯に話を聞きとめること。 |
| 共感 | 他人である相手の立場になって、理解すること。 |
| 受容 | 相手をそのまま受け入れること。否定や肯定はしない。 |
意味は少しずつことなりますが傾聴には「共感」や「受容」が大切です。この3つは他人とのコミュニケーションを図るうえでとても重要になってきます。
傾聴の効果
傾聴は相手の話を理解するだけではなく、様々な効果があります。
信頼関係が築ける
相手の話を深く聴くことで、不安、悩みを分かち合える人という安心感をもってもらえる。
話し相手の気持ちが楽になる
相手が普段はなかなか言えない話を打ちあけることで、気持ちをスッキリさせることができる。
相手の本音が分かる
相手の話を聴くことで、やって欲しいことや本当の気持ちに気付くことができる。
介護をやるうえで知識や技術だけでなく、利用者さんとの信頼関係を築くこともとても大切です。信頼関係を作ることで相手がより深い話をしてくれるようになり、お互いに壁がなくなることで気持ちが楽になります。
介護・看護での傾聴の技法・使い方
介護、看護で行う傾聴にはビジネスで使う傾聴と異なる点があります。今回は具体例を挙げて傾聴の技法や使い方、相槌や返答の仕方を紹介します。
1簡単受容
簡単受容とは相手が話している最中に話をさえぎらず「うなずく」「相槌をうつ」ことです。相手の言った言葉を少しだけ繰り返すことで、しっかり話を聴いていると相手に伝わりやすくなります。
2感情への応答
感情への応答は感情的な出来事や話を聴き、それを繰り返して伝えることです。自分の感情に寄り添って貰えていると安心感を持つでしょう。
3要約
要約とは長い話を簡潔にまとめて伝えることです。相手方の話がまとまることで考えを見直せれます。
4開かれた質問
開かれた質問とは相手が自由に答えられる質問です。相手は話すことで自分自身の理解が深まるでしょう。逆に閉ざされた質問とは「はい」「いいえ」で答えられる質問法になります。
傾聴の技法や使い方を使いこなすことで、傾聴することがあたりまえになり、利用者さんとの信頼関係が築きやすくなります。
傾聴するときに気を付けたいポイント
傾聴しているときに良かれと思って発した自分の言葉が相手を傷つけてしまう場合があります。聴くだけでなく相手の話に相槌を打ったり、質問してみるなどの言葉かけも大切です。そこで傾聴を行ううえで気を付けなければいけないポイントをご紹介したいと思います。
・アドバイスをしない。
・話を途中で遮らない。
・自分の話ばかりしてはいけない。
・軽々しく「分かります」とは言ってはいけない。
一度発してしまった言葉は取り返しがつきません。自分が言ってしまった一言で違和感を覚えた方は心を閉ざしてしまう場合もあります。全てを気を付けて傾聴することは難しいですが、覚えておくと円滑にコミュニケーションがとれるでしょう。
傾聴することの大切さ
傾聴は相手方との信頼関係を築くのにとても大切です。とくに介護現場では利用者さんとのコミュニケーションをとることが多く、傾聴する場面も増えてきます。
また相手は話すことで自分だけでは気付かなかった自分自身について理解することができます。
傾聴は看護や介護、ビジネスなどで使用される技法ですが、日常生活でも役に立つことがあるので日頃から行なうと良いでしょう。
その他のコミュニケーションテクニック
介護や医療、福祉の現場など、患者や高齢者と接することが多い仕事の方、もしくは傾聴ボランティアなど、日常会話の中で話しを聞くこととは違い、相手の気持ちに寄り添って話を受容・共感しながら聴く活動を行っている方などは、心理学の分野のことや、その他のコミュニケーションテクニックも参考になると思います。以下のようなものがあるので是非見てみてください。
ケアマネジャーの転職は、ケアマネ専門の転職サイトを利用しよう
ケアマネジャーの転職はケアマネ専門の転職サイトの利用が安心です。自分で求人を探したり、人づてに紹介してもらったりする場合、本心では希望している条件をいろいろ我慢してしまいがちになります。転職サイトを挟むことで、希望に合う職場を見つけてもらい、見学・面接対策・条件調整なども行ってもらえるので、希望理由や面接対策で悩んだりすることも減ります。新人ケアマネも、ベテランのケアマネも専門の転職サイトの方がケアマネの求人情報を多く持っています。
居宅介護支援事業所では人手不足状態、ケアマネージャー、主任ケアマネージャー資格を有する人の求人が増えています。多くの転職サイトは介護の仕事のおまけのような感じでケアマネの転職支援をしていますが、ケア求人PECORIだけはケアマネ専門なので、登録して電話面談するときにもケアマネとしての状況や今後の働き方、賃金の相場などを相談しやすいです。
「ケア求人PECOLI」は、ケアマネージャー専門の転職サイトという大変珍しいサービスで、ケアマネに特化して全国の転職支援を行っています。他の転職サイトに登録しても、よい求人が見つからなかったり、電話の人と話が合わなかったりしてうまくいかなかったケアマネも、すぐ登録できるので一度登録してピッタリな求人・転職先の紹介を受けてみましょう。(運営:株式会社PECORI 職業紹介許可番号(厚生労働大臣認可):13-ユ-308091)