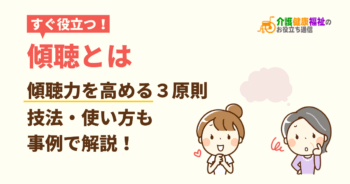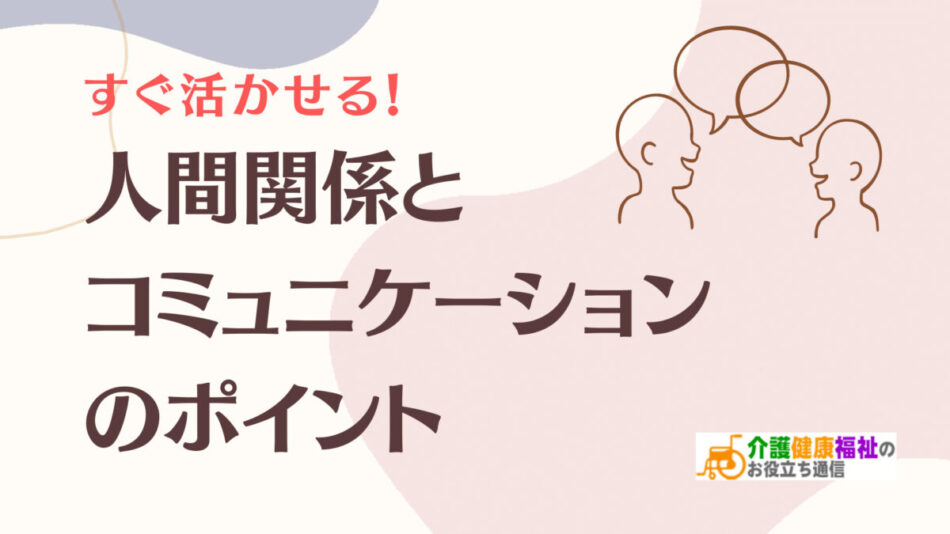好意の互恵性(こういのごけいせい)・好意の返報性という心理学の原理を紹介します。恋愛・友人関係・仕事で使える、相手に共感し、発言・考えを尊重しているサインを送るテクニックで円滑なコミュニケーション・人間関係作りに役立ちます。
好意の互恵性という言葉を知っていますか?これは心理学で扱われる概念で、「こういのごけいせい」という読み方をします。
自分はどんなとき好意を持ち、どのようにすれば自分に好意を抱いてくれるのだろうか?これは非常に興味のあることであります。
この記事では、好意の互恵性・返報性の原理という心理学について、恋愛や友人関係、仕事など実生活ではどうであるかを具体的に検証してみようと思います。
このページの目次
好意の互恵性・返報性の原理とは
好意の互恵性とは、心理学の分野で「返報性の原理」とも呼ばれます。
好意とは「その人にいだく親しみや好ましく思う気持ち」(大辞泉より引用)のことです。
好意の互恵性とは、「人は自分に好意を持っている人を嫌いにはなれない、むしろ好きになるという傾向がある」という心理学の概念です。
広告
自分と合う人はどんな人か、苦手な人はどんな人か
まず、自分がどのような友達といつもいるか考えてみましょう。考えてみると私は、自分の話や考えを熱心に聞いてくれたり、笑顔で接してくれたりする友達と自然にいつもいるようになっていました。
また、趣味が近かったり、自分に似ている部分があったりする人とも仲良くなっています。逆に、苦手な人を考えると、自分とペースが違ったり、自分の話や考えを否定したりする人です。自分が合うと思うということは、自分は相手に対して好意的に考えていて、相手も自分に対して好意的に接してくれるという相互関係があるということです。
広告
傾聴も好意のサイン そこから生まれる上手なコミュニケーション
自分の話や考えを聞いてくれるということは、自分のことを肯定してくれているようにとれます。私の話を聞きながら、うなずいてくれていたり、「そうだよね」などといってくれるだけで、「私を分かってくれている」という気持ちになり、親しみを感じます。このような時、私は相手から「好意」を受け取った状態になります。そうすると、私には「その相手とまた一緒にいたい」という感情が生まれます。好意を持ってくれていると、好意で返ってきます。これはコミュニケーションでお互いの意思疎通を行うときのベースとなります。
ソーシャルワーカーなど、相談援助を仕事にしている人には、好意の互形成・返報性を意識しつつも自己知覚しながら相手の主体を保つ技術として「バイスティックの7原則」なども活用しています。
広告
無関心や否定は敵意のサイン、敵意は敵意を生む
好意という親しみのある気持ちと反対の意味に「敵意」があります。敵意も同じように相互関係があります。否定されたり、露骨に興味がない素振りをされると、私は相手から「敵意」を受け取った状態になってしまいます。そして、「この人は苦手だ」という印象がついて敵意を抱きます。
相手から「好意」を受け取れば、自分は相手に「好意」を持ち、相手から「敵意」を受け取れば、自分は相手を「いいやつだ」とは思えず敵対的な態度になります。
広告
自分が相手を好きになることが相手から好かれるコツ
相手から好かれるために必要なことは、相手に対し好意を持つことです。
好かれたいなら、まずは相手を好きになることが大切ですということです。
具体的には、相手に共感し、相手の発言、考えを尊重することです。細かなテクニックとしては、相手の言葉やしぐさを真似するミラーリングや、相手の呼吸や無意識の動きに合わせる同調など、好意や親近感を感じてもらう方法はありますが、「心理学」とは奥の深い学問のなかで「好意の互恵性」という概念は比較的分かりやすく、そこから学んで実行しやすいです。
広告
好意の互恵性は自分のして欲しいことを相手にすること
最後に好意の互恵性・返報性の原理についてまとめると、「相手に期待する行動と同じ行動を自分が取ること」すなわち、「自分のして欲しいことを相手にすること」で、良い人間関係が築けるのです。
好意の互恵性を意識すると、相手を好きになるために笑顔でいろいろな質問や行動ができるかもしれません。
そして、その好意的なアクションは、きっと自分に返ってきて、良い関係性を構築できることと思います。
情けは人の為だけではなく、いずれ巡り巡って自分に恩恵が返ってくるのだから、誰にでも親切にしたほうが良いという「情けは人の為ならず(なさけはひとのためならず)」を学問的にしたようなものですね!
ケアマネジャーの転職は、ケアマネ専門の転職サイトを利用しよう
ケアマネジャーの転職はケアマネ専門の転職サイトの利用が安心です。自分で求人を探したり、人づてに紹介してもらったりする場合、本心では希望している条件をいろいろ我慢してしまいがちになります。転職サイトを挟むことで、希望に合う職場を見つけてもらい、見学・面接対策・条件調整なども行ってもらえるので、希望理由や面接対策で悩んだりすることも減ります。新人ケアマネも、ベテランのケアマネも専門の転職サイトの方がケアマネの求人情報を多く持っています。
居宅介護支援事業所では人手不足状態、ケアマネージャー、主任ケアマネージャー資格を有する人の求人が増えています。多くの転職サイトは介護の仕事のおまけのような感じでケアマネの転職支援をしていますが、ケア求人PECORIだけはケアマネ専門なので、登録して電話面談するときにもケアマネとしての状況や今後の働き方、賃金の相場などを相談しやすいです。
「ケア求人PECOLI」は、ケアマネージャー専門の転職サイトという大変珍しいサービスで、ケアマネに特化して全国の転職支援を行っています。他の転職サイトに登録しても、よい求人が見つからなかったり、電話の人と話が合わなかったりしてうまくいかなかったケアマネも、すぐ登録できるので一度登録してピッタリな求人・転職先の紹介を受けてみましょう。(運営:株式会社PECORI 職業紹介許可番号(厚生労働大臣認可):13-ユ-308091)