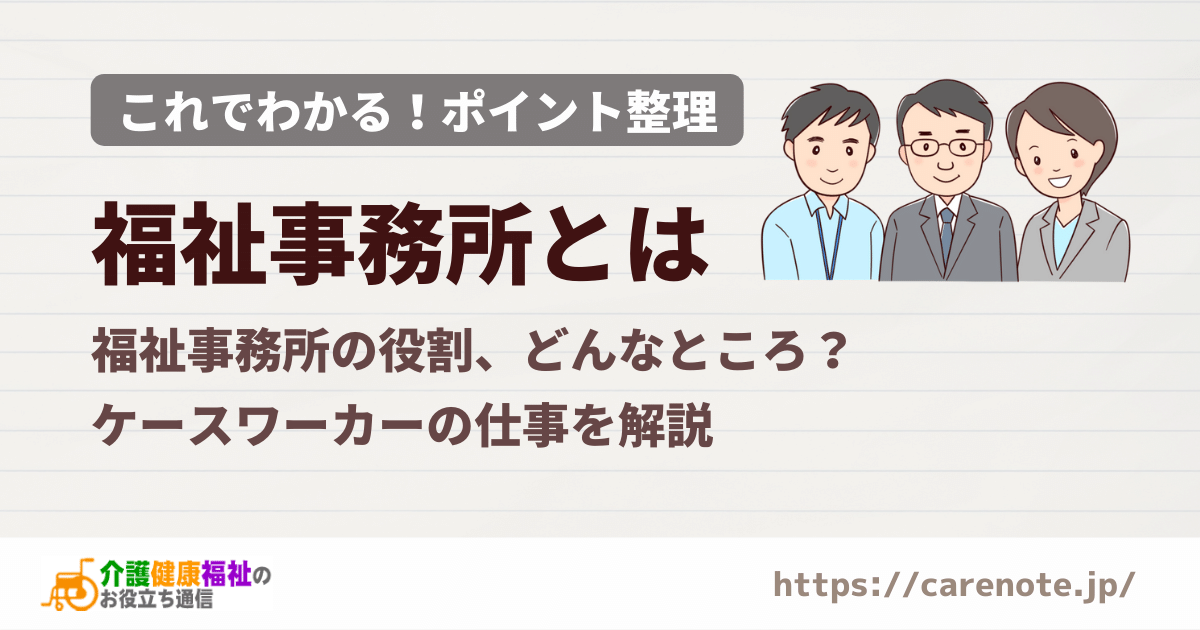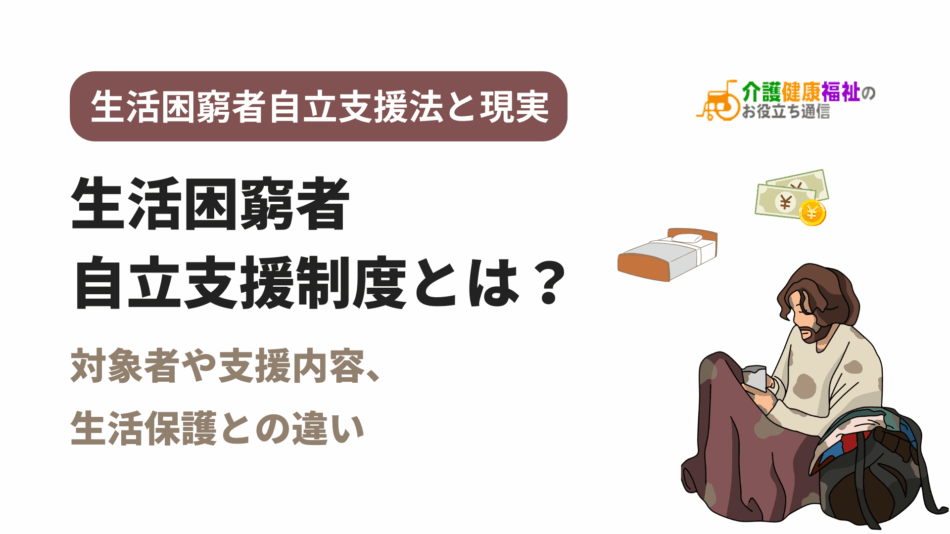
生活に困難を抱える人を支える制度といえば「生活保護」がよく知られていますが、その前の段階で利用できる仕組みとして「生活困窮者自立支援制度」があります。平成27年に施行された生活困窮者自立支援法を根拠に、相談支援や住居確保給付金、就労準備や家計改善、子どもの学習支援など幅広い取り組みが展開されています。
この記事では、生活困窮者自立支援制度の対象者や支援内容、生活保護制度との違いをわかりやすく解説し、制度の課題やデメリットについても整理します。
このページの目次
生活困窮者自立支援制度とは?
生活困窮者自立支援制度は、経済的に困難な状況にある人が生活を立て直し、自立できるように支援するための制度です。根拠法は「生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)」で、平成27年4月に施行されました。
お金の給付だけでなく、相談支援・就労準備・家計改善・子どもの学習支援などを通じて、生活の安定と自立をサポートするのが特徴です。
生活困窮者自立支援法の基本理念
(基本理念)
第二条 生活困窮者に対する自立の支援は、生活困窮者の尊厳の保持を図りつつ、生活困窮者の就労の状況、心身の状況、地域社会からの孤立の状況その他の状況に応じて、包括的かつ早期に行われなければならない。
2 生活困窮者に対する自立の支援は、地域における福祉、就労、教育、住宅その他の生活困窮者に対する支援に関する業務を行う関係機関(以下単に「関係機関」という。)及び民間団体との緊密な連携その他必要な支援体制の整備に配慮して行われなければならない。引用:生活困窮者自立支援法
同法第二条に示されるように、支援は「生活困窮者の尊厳を保持しつつ、状況に応じて包括的かつ早期に」行われることが原則です。また、福祉・就労・教育・住宅などの関係機関や民間団体との連携も重視されています。
この点から、単にお金を給付する制度ではなく、社会的孤立の解消や地域での生活再建までを含めた包括的支援が特徴となります。
まずは生活困窮者自立支援制度と生活保護制度の比較表でざっくり理解
生活困窮者自立支援制度と生活保護は混同されやすいですが、目的や内容が異なります。
| 項目 | 生活困窮者自立支援制度 | 生活保護制度 |
|---|---|---|
| 目的 | 自立の促進(生活保護に至る前の予防的支援) | 最低限度の生活を保障する最後のセーフティネット |
| 対象 | 困窮状態にあるが、生活保護には至っていない人 | 生活に必要な資産・収入がなく、自力での生活維持が困難な人 |
| 支援内容 | 相談、住居給付、就労・家計改善支援、学習支援など | 生活費・医療費などの現物給付・現金給付 |
| 給付の有無 | 一部(住居確保給付金など) | 生活費・医療費など包括的に支給 |
| 自立支援との関係 | 就労や家計再建を前提とした支援 | 生活維持を最優先。就労支援もあるが保障が中心 |
生活保護は「最低限度の生活を保障するための最後のセーフティネット」です。生活保護では生活費や医療費が公費で支給されます。
一方で、生活困窮者自立支援制度は「生活保護に至る前の段階」を対象とし、自立を促すことが目的です。現金給付は住居確保給付金など一部に限られ、基本的には相談・就労・家計改善の支援が中心です。
つまり、生活困窮者自立支援制度=予防的支援、生活保護=最終的保障という位置づけになります。
生活困窮者自立支援制度の対象者は誰か?
生活困窮者自立支援法第三条によれば、「現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者」が対象です。つまり、生活保護の手前の段階にある人が利用できます。
| 区分 | 対象となる人の例 |
|---|---|
| 収入・就労 | 失業や収入減で生活が苦しい人、就職活動中の人 |
| 住居 | 家賃が払えなくなり住居喪失の恐れがある人 |
| 家計管理 | 借金や収支管理ができず、生活再建が必要な人 |
| 社会的孤立 | 地域や社会から孤立して生活に困難を抱える人 |
| 子ども | 困窮家庭の子どもで学習支援や生活習慣改善が必要な場合 |
制度では何が行われる?
生活困窮者自立支援法に基づき、次のような事業が実施されます。自治体や委託を受けた民間団体が窓口となります。
| 支援の種類 | 内容 |
|---|---|
| 自立相談支援事業 | 生活全般の相談、支援計画作成、関係機関との連携 |
| 住居確保給付金 | 家賃を一時的に支給し、住宅喪失を防ぐ |
| 就労準備支援 | 就労に必要なスキルや社会参加の支援 |
| 家計改善支援 | 収入・支出の見直し、債務整理や貸付のあっせん |
| 居住支援 | 一定の住居を持たない人に宿泊場所や見守りを提供 |
| 子どもの学習・生活支援 | 学習援助、生活習慣改善、進路相談 |
実施主体について
生活困窮者自立支援制度の実施主体は、生活困窮者自立支援法 第5条・第6条・第7条 に基づき、制度の主要事業(自立相談支援、住居確保給付金など)は 都道府県や市町村(福祉事務所を設置する自治体) となっています。
法律第4条でも「市町村や都道府県は、生活困窮者自立相談支援事業や住居確保給付金の支給を適切に行う責務を有する」と規定されています。
委託(外部委託)の仕組み
法律 第5条第2項 により、都道府県や市町村は 「厚生労働省令で定める者に委託できる」 と定められています。実際には、次のような団体に委託されるケースが多いです。
- 社会福祉法人(例:地域の社会福祉協議会)
- NPO法人(子ども支援や就労支援を専門とする団体)
- 一般社団法人や企業(キャリア支援や相談業務に強い事業者)
制度の表現上は「委託」と呼ばれますが、実態としては 役所が責任主体となり、現場の相談や支援業務を民間団体が担う という「下請け」に近い形が広く見られます。
特に「自立相談支援事業」や「子どもの学習支援事業」は、ほぼ全国で社会福祉協議会やNPOに委託されているのが一般的です。
全国の委託状況
厚生労働省の調査によると、自立相談支援事業は、約73%の自治体が事業を「委託」または「直営+委託」の形で実施されています。事業によりますが、自立相談支援事業を例にすると委託先は社会福祉協議会(74.5%)、就労準備支援事業では9割が委託となっており、委託先は社会福祉協議会(86.5%)が最も多いです。
生活困窮者自立支援制度は役に立たないのか?
生活困窮者自立支援制度は、住居喪失や就労断絶を防ぐ効果を発揮しており、特にコロナ禍では住居確保給付金が多くの生活を支えました。しかし「相談しても十分な支援につながらない」「自治体ごとに対応が異なる」といった批判もあります。
制度の実効性は地域の取り組みや担当者の力量に左右される部分が大きいのが現状です。
制度のデメリット
金銭的給付が限定的
生活保護のような生活費全般の補填はなく、住居給付など特定用途に限られます。
自治体間格差
制度の実施主体が市町村のため、支援の手厚さや対応スピードに差が出やすいです。
利用者にとって分かりにくい
複数の事業が並立しているため、どの支援が使えるのか把握しづらいという声があります。
「自立」を前提とした支援
あくまで就労や家計改善を目指す仕組みのため、長期的に働けない人には十分ではないという批判もあります。
まとめ
生活困窮者自立支援制度は、「生活保護に至る前に支援する」ための包括的な仕組みです。生活困窮者自立支援法を根拠に、相談支援・住居給付・就労訓練・家計改善・子どもの学習支援など幅広い取り組みが行われています。
ただし、金銭給付の限界や自治体格差、制度の分かりにくさなどの課題も抱えています。制度を「使えない」と感じる人がいる一方で、住居喪失や生活破綻を防いだ実績もあります。利用者自身と支援者が制度の特徴を理解し、必要に応じて生活保護など他制度と組み合わせていくことが重要です。
参考:生活困窮者自立支援法等に基づく各事業の令和5年度事業実績調査集計結果(厚生労働省社会・援護局 地域福祉課生活困窮者自立支援室)