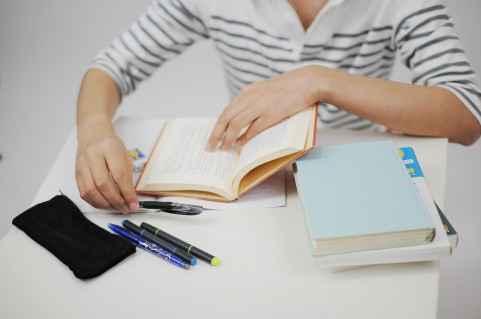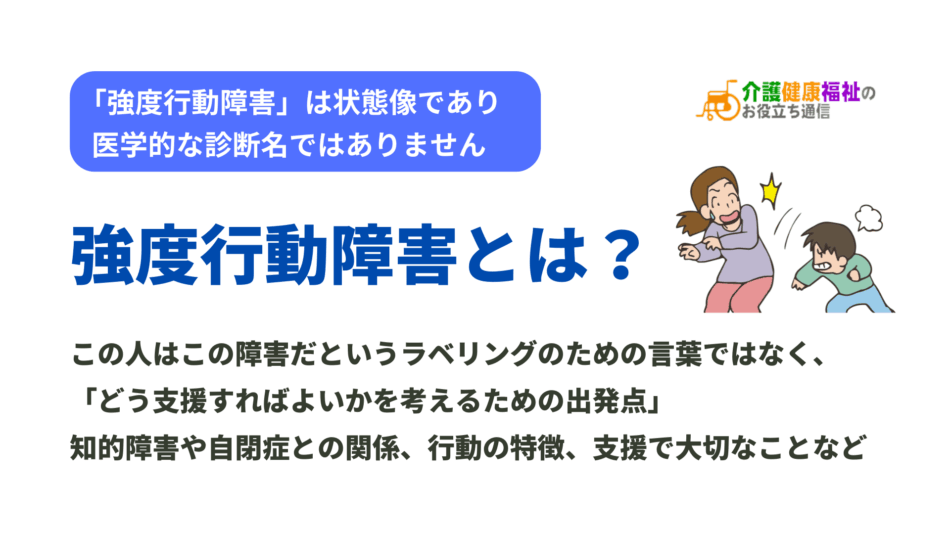
強度行動障害は、自傷や他害、破壊行動など、日常生活に重大な支障をきたす深刻な行動特性を持つ状態を指します。その背景には、重度の知的障害や自閉症スペクトラム障害などの発達特性、または言語による意思疎通の困難さ、不安や感覚過敏などが複雑に絡み合っています。家族や支援者は、ただ行動を抑えるのではなく、「なぜその行動が起きているのか」を理解し、適切な支援や環境調整を行う必要があります。本記事では、強度行動障害が生じる背景、症状の特徴、チェックリスト、対応方法、そして保護者支援の視点まで、支援の現場に役立つ知識を丁寧に解説します。
このページの目次
強度行動障害とは何か?
強度行動障害とは、日常生活に重大な支障を及ぼすような、極めて強い問題行動を継続的に示す状態を指します。これには自傷、他害、物の破壊、常同行動、強い不安などが含まれ、介護者の安全確保や生活の質の維持すら困難になるケースもあります。特別支援教育や障害福祉分野では、通常の支援だけでは対応が難しく、個別の専門的な支援が必要とされる対象です。
「強度行動障害」は状態像であり医学的な診断名ではない
「強度行動障害」という言葉は、DSM-5(精神疾患の診断・統計マニュアル)やICD-10/ICD-11(国際疾病分類)などの医療的診断基準には記載されていない用語であり、あくまで支援や福祉の分野で使われる支援上の概念です。
つまり、「自閉スペクトラム症」や「知的障害」といった医学的な診断がある人の中で、非常に強い行動上の困難(自傷・他害・破壊・常同行動など)を持ち、日常生活や支援が極めて困難な状態にあることを表すために用いられます。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 診断名かどうか | 医学的な診断名ではなく、支援上の分類(状態像) |
| 用いられる分野 | 福祉、教育、支援制度(特別支援学校、障害福祉サービス等) |
| 該当しやすい診断名例 | 知的障害、自閉スペクトラム症、てんかんなど |
| 活用される制度 | 強度行動障害支援加算、特別支援教育の個別支援計画、支援者研修など |
「強度行動障害」はこの人はこの障害だというラベリングのための言葉ではなく、「どう支援すればよいかを考えるための出発点」として活用されるものです。支援現場でこの用語を使うときは、その文脈と意味を丁寧に伝えることが大切です。
発生の原因と背景にある要因
強度行動障害は、単一の原因で起こるものではありません。背景には、重度の知的障害や自閉症スペクトラム(ASD)の存在、感覚の過敏性や不安障害、言葉での表現力の乏しさ、環境への適応の難しさなど、複数の要因が重なって発生すると考えられています。
たとえば、自分の思いを言葉で伝えられないことでフラストレーションが高まり、自傷行動や他害行動に発展するケースもあります。また、周囲の環境変化に対する強いストレスや、スケジュールの変化なども誘因となり得ます。
知的障害や自閉症との関係
強度行動障害のある子どもの多くは、重度の知的障害や自閉症スペクトラム障害(ASD)を併せ持つ傾向があります。特に、言語理解や表出の困難がある場合、周囲との相互理解が築けず、自己表現の手段として極端な行動に頼るようになるリスクが高まります。
また、自閉症の特性である感覚過敏やこだわりの強さも、突発的な環境変化や不快な刺激によって、行動の爆発につながることがあります。
強度行動障害のチェックリスト
以下のような行動が複数、かつ日常的に見られる場合は、強度行動障害の可能性を考慮し、専門機関への相談が必要です。
| 行動の種類 | 具体例 |
|---|---|
| 自傷行為 | 頭を打ち付ける、腕を噛む、目を押すなど |
| 他害行為 | 他人への噛みつき、叩く、物を投げるなど |
| 破壊行為 | 家具を壊す、物を投げて破壊するなど |
| 常同行動 | ずっと同じ動作を繰り返す、叫び続けるなど |
| 社会的問題行動 | 着替えを拒否する、外出を極端に嫌がるなど |
噛みつきや破壊行為、他害などへの対応方法
強度行動障害への対応では、行動そのものを抑えるのではなく、「なぜその行動をとるのか」という背景や目的を理解することが第一歩です。具体的な対応としては以下のような方針が考えられます。
| 観点 | 具体的な対応内容 | 目的・狙い | 効果・注意点 |
|---|---|---|---|
| 構造化された環境の提供 | ・スケジュール表(絵カードやタイマー)を使って、1日の流れを視覚的に示す
・活動の予告や切り替え時の合図を一定にする |
不安を軽減し、次に何が起きるかを本人が予測できるようにする | スケジュールの「変更」がストレスになる場合もあるため、変更時は事前予告や安心できる支援者の関与が必要 |
| 意思表出の代替手段の提供 | ・PECS(絵カード交換式コミュニケーション)
・タブレットの音声アプリ ・簡単なジェスチャーや指差しなど |
言語で表現できない不快や要求を、別の手段で表せるようにする | 使用方法の学習が必要なため、支援者や家族による継続的なサポートが求められる |
| 行動の記録と分析 | ・「ABC分析」などを用いて行動の前後の状況を記録
・トリガー(引き金)やパターンを探る |
問題行動の「機能」(何を目的としてその行動をしているか)を把握する | 行動が起きた直後の状況だけでなく、身体的・感覚的な状態にも注目することが重要 |
| 身体的制止(最終手段) | ・自傷や他害が切迫している場合に、一定の距離をとって安全確保
・「非接触の制止」から優先 |
本人・他者・支援者の命や身体を守るための最低限の対応 | 制止がトラウマになる恐れがあるため、事後に必ず「安心感」を回復させる声かけや関わりが必要 |
| 関わり方・声かけの工夫 | ・短く、わかりやすい言葉で指示する
・指示は肯定文(「〜してね」)で伝える |
混乱を最小限にし、行動への切り替えを支援 | 怒鳴ったり否定語で指示することは、逆効果になる場合が多い |
強度行動障害の支援で大切なこと
強度行動障害のある子どもへの支援で重要なのは、「その行動が何を伝えようとしているのか」を汲み取る姿勢です。行動を「悪いこと」と見なすのではなく、「助けを求める手段」や「自己表現」であると捉え、共感的に受け止めることが必要です。
また、支援者自身が「成功体験」を共有することも大切です。うまくいった関わりや、行動が減少した際の要因をチームで共有し、支援方法を可視化することが、継続的な支援の質を高めます。
保護者を支えるためにできること
強度行動障害のある子どもを育てる家庭では、日々の対応の中で心身ともに疲弊し、孤立を感じやすくなります。支援者や周囲の人ができることは次の通りです。
| 支援内容 | 具体的な方法 | 支援の目的 | 留意点・効果 |
|---|---|---|---|
| 相談の場の提供 | ・学校や事業所での定期的な個別面談
・家庭訪問支援 ・オンライン相談の導入など |
保護者が悩みを言語化し、孤立感を軽減できるようにする | プライバシーや否定的な評価への不安に配慮し、受容的な姿勢で対応することが信頼形成の鍵 |
| 肯定的フィードバックの共有 | ・「今日は落ち着いて座れていましたね」など、具体的な成長を伝える
・失敗ではなく努力の過程を褒める |
保護者が自分と子どもの努力を認められることで、支援に前向きになれる | 褒める際は「親の努力」も一緒に認めると、自己肯定感が高まりやすい |
| レスパイトケアの提案 | ・短期入所(ショートステイ)
・日中一時支援サービス ・放課後等デイサービスの紹介 |
保護者が休息をとることで、心身のリフレッシュや介護疲労の蓄積を防ぐ | 「手を抜いてよい」と保護者が安心して預けられるよう、制度の説明や利用体験談を共有する |
| 専門機関とのつなぎ役 | ・発達障害者支援センター、精神科医、療育センター、福祉相談窓口などを紹介
・申請書類の書き方を支援 |
保護者が複雑な制度に迷わず、必要な支援に早期にアクセスできるようにする | 書類や制度が難解な場合が多く、「一緒に確認しましょう」と寄り添う姿勢が重要 |
| 情報提供とピアサポートの案内 | ・自治体の支援制度、助成制度、相談会、保護者会などを案内
・同じ立場の保護者との交流を紹介 |
保護者が「ひとりじゃない」と感じられる居場所づくり、実践的な情報収集の機会となる | 支援のゴールは「情報の伝達」ではなく、「安心できるつながり」を感じられる場の提供であるべき |
まとめ
強度行動障害は、子どもの内面の苦しさや環境への適応の難しさが、行動という形で表れている状態です。適切な理解と支援があれば、行動は落ち着き、本人も周囲も安心して暮らせるようになります。否定ではなく共感から始める支援が、本人の生きやすさと家族の希望を育んでいく第一歩となるでしょう。
参考:強度行動障害のある児童・生徒への効果的な指導の在り方(東京都教育委員会)
障がい者におすすめの転職エージェント
障がい者としての転職をするのは抵抗があるかもしれませんが実際にどんな求人があるのか、どれくらいの給料でどんな条件なのかについてはサイトで確認することができます。
障害者の就職・転職ならアットジーピー【atGP】
「アットジーピー【atGP】」は、障害者雇用のパイオニアとして、15年以上に渡り障害者の就職・転職をサポートしてきた企業です。会員登録をしない状態でも一般的な転職サイトのように障がい者向けの公開求人情報を確認でき、給料や条件を見れるのが特徴です。会員登録すると一般には公開されていない、優良企業の求人などもあります。