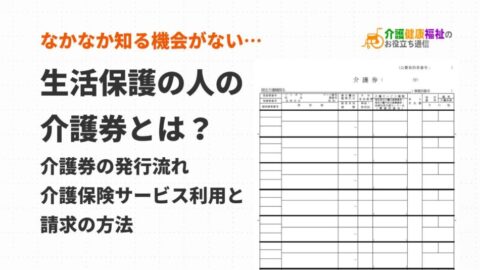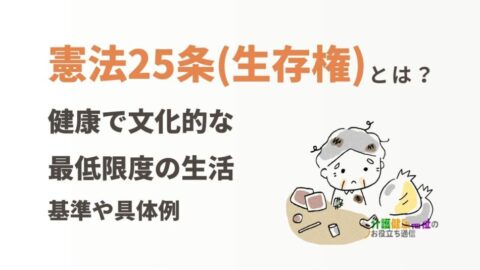人生会議とは?もしもの時の医療やケアの話し合いとお金の問題
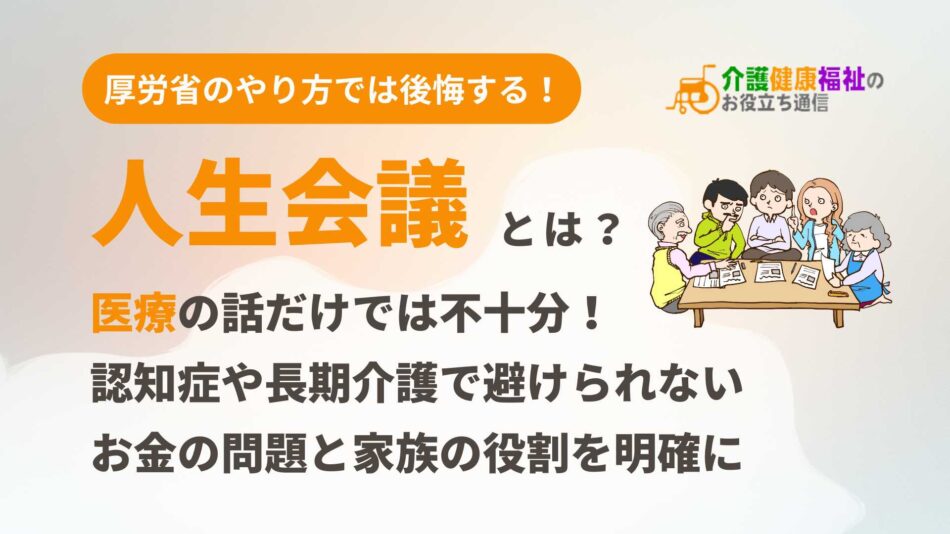
この記事はプロモーションが含まれます。
人生の最終段階や、もしもの時の医療・ケアについて事前に話し合う「人生会議(ACP)」が注目されています。
厚生労働省は、延命治療や看取りの希望を家族や医療・介護の専門職と共有し、本人の意思を尊重したケアを実現する取り組みとして人生会議を推進してきました。
一方で、ポスター炎上の事例に象徴されるように、啓発活動は必ずしも順調ではありません。しかし、医療・介護の現場で長年利用者と家族に関わってきた筆者としては、人生会議は「医療選択の話」だけでは十分ではなく、認知症や長期介護で避けられないお金の問題と家族の役割こそ、真剣に話し合うべきだと考えています。
この記事では、厚生労働省が定義する人生会議の基本から、実際の介護現場で頻発する家族間トラブル、財産管理の課題、そして筆者が提案する本当に必要な人生会議の姿まで、専門家の視点で詳しく解説していきます。
いま「人生会議」が必要とされる理由
近年、医療・介護の現場では「人生会議(アドバンス・ケア・プランニング:ACP)」という言葉を耳にすることが増えています。厚生労働省や神戸大学などは、将来の療養や介護が必要になった時に備え、延命治療、蘇生措置、看取りの場所などについて、本人・家族・医療・介護の専門職が事前に話し合い、共有しておくことを推進しています。
人生会議は「もしもの時のために備える」ために大切ですが、現場で実際に介護に関わってきた筆者としては、医療やケアの希望だけでは不十分であり、長期の介護において避けられないお金と支える家族の負担を含めて考えるべきだと強く感じています。
医療や介護の業界では、常々患者や利用者本位のケアや、その人が望む生活ということを重要視しており、医療介護職に無理強いをしてでも患者さんやご利用者の権利を守るべきというような倫理観が強いられています。
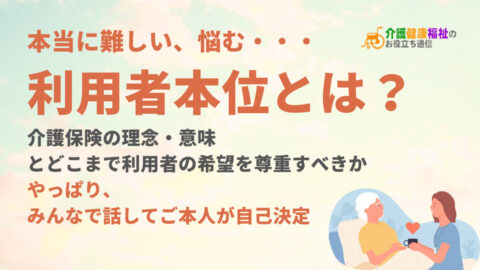
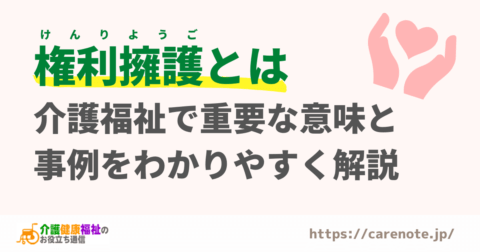
人生会議とは何か ― 厚生労働省の定義
厚生労働省は人生会議(ACP)を次のように定義しています。
「将来の変化に備えて、本人が大切にしている価値観や望む医療・ケアについて、家族や医療・介護チームが繰り返し話し合い、共有する取り組み」
人生会議は一度きりの話し合いではなく、病状や家族状況が変化した際に見直すプロセスとされ、本人の意思を尊重しながら最適なケア方針を選択することが目的とされています。
また厚生労働省は、人生会議を普及させるために、ポスター・冊子・人生会議ノートを配布するなど啓発活動を継続してきました。しかし過去には、お笑い芸人を起用したポスターが「死を笑いの道具にしている」「恐怖を煽る」などと批判され炎上した経緯もあり、啓発の方向性や伝え方については難しさが指摘されています。

人生会議が推進されるのは、医療介護側のリスク回避という側面
人生会議は本人と家族のために重要であると同時に、医療・介護現場にとっても必要性があります。
延命治療や蘇生措置、人工呼吸、経管栄養などの判断について、患者本人の意思が不明確な状態だと、医療者が望まない治療と後になって恨まれるリスクがあります。
過去には「治療方針を決めてくれなかった」「望まない延命をされた」と家族が医療機関を訴えるケースもあり、治療方針を事前に確認しておくことは医療者にとっても重要な安全策といえます。
そのため人生会議の普及は、本人の尊厳のためだけでなく、医療機関や医療者のリスク管理としての側面もあることは、正しく理解しておく必要があります。
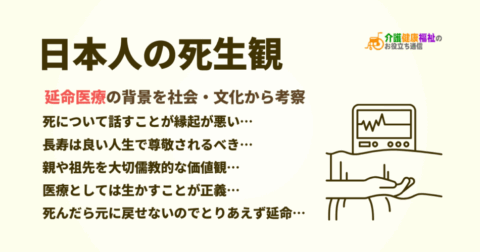
筆者が考える人生会議、医療とケアだけでは不十分
筆者は長年、高齢者の介護と療養の場に関わってきました。その中で痛感しているのは、人生会議が医療と介護の希望の共有だけにとどまることの危うさです。
人生会議のポスターやガイドブックでは、
「延命治療を望むか」
「どこで最期を迎えたいか」
「どんなケアを希望するか」
といった内容が中心ですが、現場の実態ではこれだけでは問題の半分にもなりません。
どんなことでもそうですが、「希望する内容」と「お金の問題」を並べて考えないといけないのですが、そうはなっていません。もちろん、日本には国民皆保険の制度があり、医療費が高額になった場合にも上限額があるので、一時的であれば実質的に保険適用の範囲内の医療や介護は受けることができる人が多くいらっしゃいます。また、2025年時点ではまだ後期高齢者医療制度により高齢者の医療費は現役世代よりも自己負担が少なくなるので、その点でも医療を望むならば受けやすい状態ではあります。
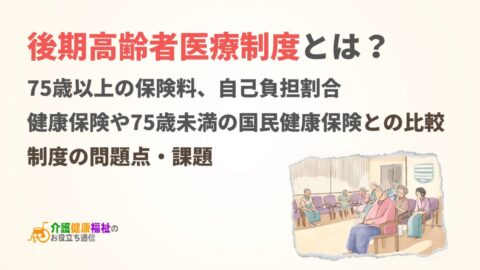
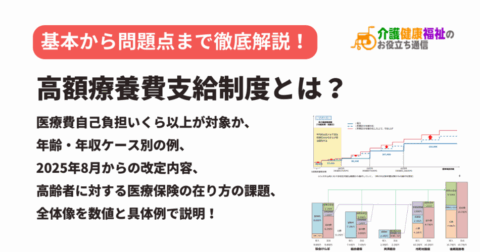
人生会議が大切であると啓発することは国としても良いことですが、これは国とその社会保障の事業を肩代わりしている介護保険施設や医療機関が、なるべくたくさんの医療や介護を提供するための最大値を確認したいという意味合いも強く、医療や介護を提供してしまえば回収できる医療機関側の人間に都合が良い取り組みです。
人生なので、医療や健康状態だけではなく、本当はお金の面が重要ですが、この人生会議という概念自体、厚生労働省が医療系の人たちと作っているためにやり方や観点として医療面に偏ってしまっています。
つまり、今厚生労働省が進めているのは「医療機関の売上と社会保障費の増大にどれだけ貢献するかの会議」に近いのです。
何も希望しなければ、基本的にはフルコースで医療が提供されることになると思いますが、そのフルコースの医療から本人がやってほしくないことを共有しておくという意味合いが強いです。もちろん今まで多くの人にフルコースの医療が際限なく使われて、それにより社会的入院や長期間の寝たきり、苦痛を伴った延命までいろいろなケースがありました。
少し半サロ的な主張となりますが、この過剰医療により、家族の人生まで親の介護や医療にずっと関わり続けるという状況や、社会保障費が膨れ上がり続ける状況だったので、厚生労働省は進める人生会議で少しでもそのようなケースが減るのは価値はあると思います。
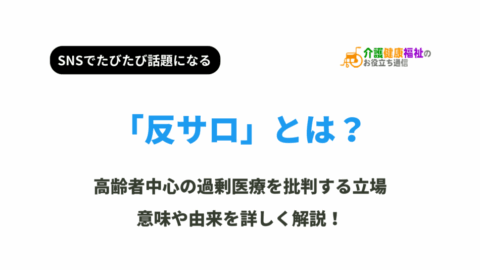
認知症と長期介護の現実 ― 医療よりも深刻なお金と家族の摩耗の問題
認知症は進行とともに判断力が低下し、銀行手続きや契約ができなくなります。
そうなると、どんなに良い家族関係があっても、長期間にわたる介護の負担が家族を疲弊させ、結果として恨みや対立につながることが現場では珍しくありません。
筆者が関わってきたケースでも、以下のようなトラブルが頻繁に発生してきました。
- 長期間の介護により息子や娘が生活を圧迫され、兄弟間で不満が爆発する
- 親の医療費や介護費用を誰が負担するかで険悪になる
- 認知症発症後に財産管理ができなくなり、親が子へ支援したいと思っても手続きができない
- 不動産を多く持つ人でも、認知症後は売却・管理・賃貸契約ができず凍結状態になる
これらは、人生会議が取り上げる医療・ケアの希望だけでは解決できません。高齢社会になり「延命」や「介護」については社会的にも認知され、考える人は増えてきました。しかし、それに伴うお金のことや、家族での分担までは具体的には考えていないのが現状です。
認知症初期もできる・未来を見据えた家族信託を支援している、家族信託コンサルタントの「横手彰太」さんも、少しずつ元気なうちに、精神的にも経済的にも人生のバトンをつないでいくことが大切と発信しています。認知症とお金の問題、親の介護の現実と財産管理の方法として、家族信託という選択肢はその中でも特に重要な点であることと訴えています。
認知症になった後では遅い、なぜ財産と役割の話し合いが必要なのか
認知症発症後は、本人名義での新しい契約、財産管理、不動産の売却・賃貸、贈与などは大きく制限されます。
そのため、たとえば本人が「いつも介護してくれる息子に住宅資金を援助したい」と思っても、認知症が進行した後では実現できないケースが多くあります。
また不動産を持っていても、信託契約や財産管理契約を結んでいなければ、管理も売却もできず、家族が介護費や生活費に困窮する状況が起こりえます。
介護や医療の業界に関わっている人は、認知症の患者さんや利用者さんについてのやり取りで「成年後見人」という言葉は聞いたことがあると思いますし、関わったことがある人も多いと思いますが、実際特に何もしてくれないというのが現状だとなんとなく感じていると思います。
また、キーパーソンだとしても、法定代理人や信託契約を結んでいない限り認知症の親の財産を勝手に売却したりはできないということもなんとなくわかると思います。仮に老後2000万円が必要だからと、親の口座に2000万円頑張って貯めていたとしても、親が認知症になってしまって銀行口座の出金が制限されてしまった場合には、家族であっても簡単には引き出すことができなくなります。
ケアマネの仕事などをしていると、認知症になった後の介護のことやお金のことで家族が疲弊していることに接することも多くあると思います。
筆者としては、人生会議こそ「財産管理」と「家族の役割」を含めて話し合うべきだと考えています。
むしろ資金計画と家族の役割の話を抜きに人生会議をしたとしても、絵に描いた餅でしかありません。
話し合うだけでは法的な面で意味を持たないので、専門家を交えて家族に信託契約のような形で法的にも意味がある形にしないといざという時実行することはできません。
これは単に家族の負担軽減のためではなく、最終的には本人が望む暮らしを継続するために不可欠な視点です。
参考:認知症の親の介護費用を親の口座から引き出すのは法的に問題ない?
本当に必要な人生会議とは ― 医療・ケア・お金・家族の役割を統合した話し合い
筆者が提案したいのは、次の要素を統合した人生会議です。
| 話し合うべき内容 | 具体的に確認すべきこと |
|---|---|
| 医療面 | 延命治療、蘇生措置、人工呼吸、経管栄養、看取り場所 |
| 介護面 | 在宅か施設か、誰が介護を担うか、専門職との連携 |
| 財産面 | 認知症になる前に信託契約や財産管理委任をどうするか |
| 家族の役割と負担 | 誰が介護参加するのか、介護費用分担はどうするのか、家族間で公平性をどう保つか |
| 将来のキャッシュフロー | 介護費・医療費・生活費を長期間どう維持するか |
厚生労働省の人生会議は重要ですが、それだけでは人生の全体像を守りきれません。
医療とケアだけでなく、お金と家族関係に踏み込むことが、真の意味での人生会議になると筆者は考えます。
人生会議は「命の話」だけではなく、本来は「生活と財産の話」である
人生会議は、とても大事な取り組みです。
しかし、医療・介護の希望だけに偏ると、認知症や長期介護の現実に対応できず、本人にとっても家族にとっても不幸な結果を招くことがあります。
筆者としては、次の視点が人生会議の本質だと考えています。
人生会議は終末期の話し合いではなく、これからの人生と家族を守るための包括的な準備である。
医療・ケア・財産・家族の役割を総合的に話し合うことが、
本人の尊厳を守り、家族の摩耗を避け、円満な介護・療養を実現するために不可欠です。
人生会議は、未来の自分と家族のための最も実践的な備えと言えます。