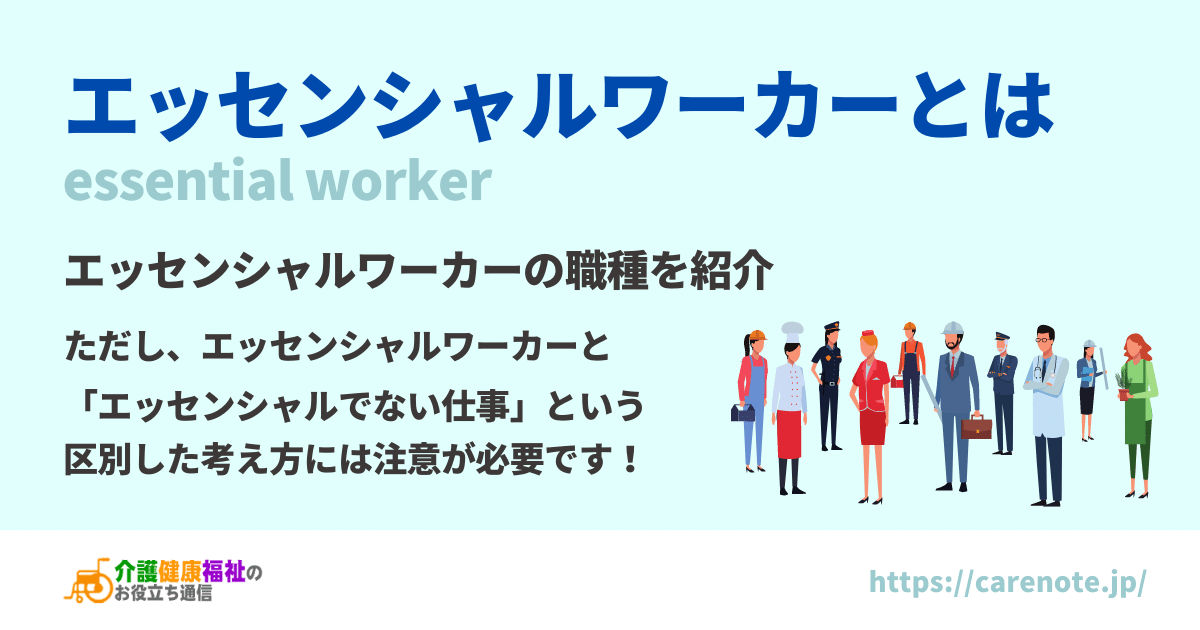仕事の種類を表す言葉としてよく耳にする「ホワイトカラー」と「ブルーカラー」。ホワイトカラーは知識や情報を扱うデスクワーク中心の職種、ブルーカラーは体を使い社会の基盤を支える職種とされています。
近年はホワイトカラー志向が強まり、ブルーカラーの人材不足が深刻化していますが、どちらも社会に欠かせない存在です。では、介護職や看護師はどちらに分類されるのでしょうか。実は、その答えは一方に決めつけられるものではなく、両方の要素を兼ね備えているのです。
この記事では、ホワイトカラーとブルーカラーの違いを整理しながら、介護や看護の仕事の位置づけについて考えていきます。
このページの目次
ホワイトカラーとは何か
「ホワイトカラー」は英語で「White Collar」と表し、白いワイシャツを着る仕事ということに由来した言葉と言われています。
ホワイトカラーとは、主にオフィスや屋内でのデスクワークを中心に行う職種を指します。
経理や総務、営業、ITエンジニア、研究者などが代表例です。知識や情報を扱い、肉体労働よりも頭脳労働が中心となります。
近年では「ホワイトカラー・エグゼンプション」という制度も議論されており、労働時間ではなく成果に基づいて賃金を決めるという特徴も出てきました。高学歴化に伴い、ホワイトカラー志向は強まっていますが、その一方で「生産性の低いホワイトカラー」も存在し、社会的な課題とされています。
ブルーカラーとは何か
「ブルーカラー」は英語で「Blue Collar」、青い作業服の襟が職業の象徴となったことに由来しています。
ブルーカラーは、製造業や建設業、運送業などに代表される肉体労働を中心とした職種を指します。現場での作業や体力を伴う仕事が多く、インフラ整備や建築、物流といった社会基盤を支える役割を担ってきました。日本の高度経済成長を下支えしたのはまさにブルーカラーの力であり、現在でも建物や道路、橋梁などのメンテナンスを担う人材は不可欠です。しかし、若い世代の志望者減少により、人材不足が深刻化しています。
ホワイトカラーとブルーカラーの比較表
| 項目 | ホワイトカラー | ブルーカラー |
|---|---|---|
| 主な仕事内容 | デスクワーク、企画、管理、営業、研究、ITなど | 製造、建設、運送、整備、介助など体力を伴う作業 |
| 労働環境 | 屋内中心、オフィス勤務が多い | 屋外や現場勤務が多い |
| 必要とされるスキル | 知識、判断力、情報処理能力、コミュニケーション | 体力、技能、実務経験、安全意識 |
| 学歴の傾向 | 高学歴志向が強い(大卒以上が多い) | 学歴に関わらず就ける職種が多い |
| 成果の形 | 書類やデータ、企画提案など「形のない成果」 | 製品、建造物、インフラなど「形に残る成果」 |
| 課題 | 生産性の差が大きく、成果が見えにくい場合がある | 人材不足や労働環境の厳しさが深刻化 |
| 社会的役割 | 経済や組織運営を知識で支える | 社会の基盤や生活環境を現場で支える |
介護職や看護師はホワイトカラー、ブルーカラー、どちらの要素も併せ持つ
介護や看護の仕事をしていると、「自分はブルーカラーなのかホワイトカラーなのか」と考えたことがある人も多いでしょう。
介護や看護の仕事を見ていくと、ホワイトカラーとブルーカラーの両方の特徴を色濃く含んでいることが分かります。日々のケアでは、利用者の体を支えたり移乗を行ったりするなど、明らかに肉体労働的な要素があり、ブルーカラーに近い働き方です。一方で、利用者や患者の症状を観察し、記録をまとめ、医師や他職種と連携して判断や対応を行う部分は、知識と情報を扱うホワイトカラー的な側面です。
さらに介護や看護の成果は、建物や製品のように物理的に残るものではなく、人の暮らしや健康をその瞬間ごとに支える「目に見えにくい価値」です。そのため、生産性や効率性だけでは測れない領域が多く存在します。ブルーカラーが社会の基盤を築き、ホワイトカラーが知識を活用するように、介護や看護は「人の生活を守る基盤」を提供しているのです。
介護・看護という仕事の価値の捉え方
介護や医療の仕事は、目に見える「モノ」を生み出すわけではありません。利用者が亡くなれば、その人に提供したケアは物理的には何も残らないのが現実です。そのため「生産性」で単純に測ると、建設や製造のように形ある資産を残すブルーカラーの仕事に比べて見劣りするという議論が出ることもあります。
しかし、利用者や患者の生活の質を支えることは、社会的に大きな事業です。ブルーカラーが社会基盤を作り、ホワイトカラーが知識を生かすように、介護や看護は「人の暮らしを支える基盤」を築いています。
介護職や看護師はどちらでもある
介護や看護はホワイトカラーでありブルーカラーでもある、境界を超えた職業です。体力を使いながらも知識と判断力を活かす、そしてモノではなく人の生活を支えるという独自の価値を持っています。介護職や看護師の働きは社会保障の分野が中心になるので、国レベルでは国家予算の多くを医療や介護に投入していて、生産性では単純に測れないとはいえ、生産的な分野や、国家を維持するために未来に必要な分野で活躍する人が増えないと、なかなか難しい局面に来ていると思います。
管理的で創造的な仕事も、体力を使う仕事も、お互いに関心を持とう
介護職や看護師はエッセンシャルワーカーで重要な役割をしているというのは確かなことですが、その他の職業の人たちも必要な仕事をしています。
介護や医療に関わる人は、自分たちの職域にしか関心が湧きにくく、自分たちの処遇改善や、自分たちだけがこんなに頑張っているということを独りよがりに訴える傾向があります。
ブルーカラーやホワイトカラーという区分は気にせず、他の人がどんな仕事をしているのか、今後どんな仕事が社会や世の中のために重要になっていくのかということも考えることも大切です。