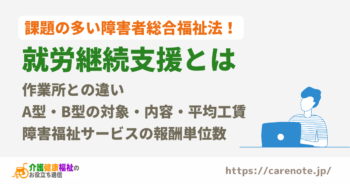障害者の就労と社会参加を両立をする福祉拠点のパン屋さんを例に、障害者は隠せの文化から脱却し就労と社会参加を促すときに自立支援法の矛盾問題について紹介します。
このページの目次
『利用料』を支払って、労働体験サービスを利用する障害福祉サービス
タウンニュース 記事
障害者が就労継続支援施設などで作ったパンを、店頭販売する仕組みとなりました。
このような取り組みは、特別新規性があるわけではなく、近年社会福祉法人やNPO主体の授産施設などで増えてはいます。しかし、ほとんどが「障害福祉サービス」という国の枠で行われています。
障害福祉サービスは介護保険などと同じで、『利用料』を支払って、労働体験サービスを利用する形になっています。
超大問題なのである。それぞれの施設や自治体で差はあるが、工賃1万円 利用料は3万円などと言われています。
1級身体障害者で障害年金が月7万円程度で、その他の手当てがあっても生活が困窮してしまう厳しい利用料となっている。
工賃から利用料や指導料などを支払うとタダ働き以上だったりすることもあります。
運営する法人の方も何とか工賃を捻出していますが、障害福祉サービスの仕組みがいろいろ困難な問題を抱えていることは確かです。また、良心的に福祉を提供しようと考えている事業者だけでなく、障害福祉サービスの枠組みになってからは民間からの参入も増えていて就労継続や就労への移行という目的があいまいでビジネスとして捉えられてしまっていることにも制度上の課題があります。
広告
江戸時代には見世物小屋の文化が存在した
話は脱線しますが、障害者のことを考えるとき「人権」や「差別」の話になることが多です。
その時、日本には「見世物小屋」という文化があったことがあまり語らせることは無いですが、結構重要なことだと思います。
お代は見てからで結構だよ。さあさあさあさあ入って入って、間もなく始まるよ〜。
道端や広場でこのような掛け声で客を集めて、今で言うパフォーマーや大道芸人のようなノリで障害者が働いていました。
何を見せていたかというと、奇形の子供、身体障害者、性行為などを覗き穴で見せるなど、文字通り何でも見世物にしていたのです。
はじめは大道芸のようなものや、珍しい動物等だったようですが、後には手足のない女性(通称だるまおんな)など、現代では明らかに人道を外れていることが普通にありました。
しかし、お客の方から、可愛そうとか面白いとか、なんかしらの感動の類があり、興行収入を稼いでいたのです。
現代の価値観や思想では、明らかにこれらは差別でひどい扱いですが、現代もまた違った形で障害の溝は残っています。
それは、支援する人と、サービスの利用者という関係性です。
人権や社会福祉の整備がなされ、みんな平等、差別はしないという形になりながら、一部では差別を招いてしまったのかもしれません。
就労はできても、生活に必要なお金が稼げるかが焦点
一般企業には、障害者の就職を支援するために、障害者雇用促進法を作り、企業に対して、雇用する労働者の2.0%に相当する障害者を雇用することを義務付けています。
その枠で就職すれば、とりあえず最低賃金以上の賃金が支払われます。(たくさん障害者雇用したら、企業はその分の補助を受けたりできる)
厚生労働省 障害者雇用対策
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/index.html
その他の場所では、なかなか雇用と報酬が実現できません。
このようなパン屋さんのような取り組みから、障害のある方の就労や活躍が評価されていき、支援者とサービス利用者という関係性から少しでも対等でどちらも幸せな関係性が作れたらと思います。
障がい者におすすめの転職エージェント
障がい者としての転職をするのは抵抗があるかもしれませんが実際にどんな求人があるのか、どれくらいの給料でどんな条件なのかについてはサイトで確認することができます。
障害者の就職・転職ならアットジーピー【atGP】
「アットジーピー【atGP】」は、障害者雇用のパイオニアとして、15年以上に渡り障害者の就職・転職をサポートしてきた企業です。会員登録をしない状態でも一般的な転職サイトのように障がい者向けの公開求人情報を確認でき、給料や条件を見れるのが特徴です。会員登録すると一般には公開されていない、優良企業の求人などもあります。