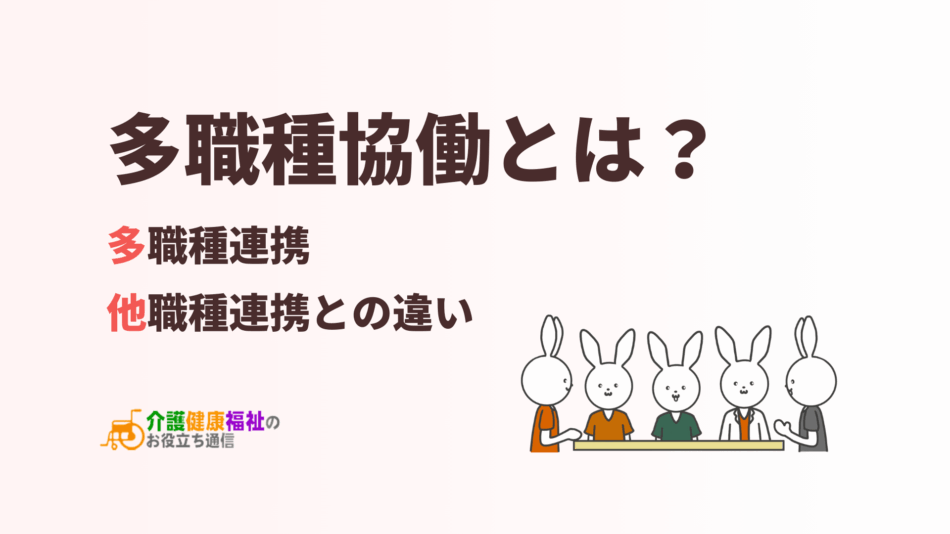
介護や医療、福祉の現場では「多職種協働」という言葉を耳にする機会が増えています。制度や省令でも頻繁に使われる用語ですが、似た表現として「多職種連携」や「他職種連携」も存在し、混同されやすいのが実情です。現場で求められる専門職同士の関わり方を理解するためには、これらの言葉の意味と違いを整理しておくことが重要です。
この記事では、多職種協働の定義を確認した上で、「多」と「他」の言葉の違いに注目し、介護保険制度における位置づけも含めて解説します。
多職種協働とは何か
「多職種協働」とは、介護・医療・福祉の現場で、異なる専門職がそれぞれの専門性を尊重しながら共通の目標に向かって力を合わせることを指します。単に情報をやり取りするだけではなく、互いに補い合い、利用者本人や家族の生活を支えるために協力して実践する姿勢が強調されます。介護保険の省令や制度文書でも「協働」という言葉が使われており、チームとしての一体感や対等性が意識されている点が特徴です。つまり、多職種協働は制度用語としても現場用語としても定着しており、単なる連携以上の「一緒に働く」意味合いを含んでいます。
違いを整理した比較表
| 用語 | 意味 | ニュアンス | 制度上の位置づけ |
|---|---|---|---|
| 多職種協働 | 複数の専門職が対等に協力して働くこと | 「共に働く」強調 | 省令などで使用 |
| 多職種連携 | 多様な専門職による情報共有と役割分担 | 「多様性とつながり」強調 | 現場やガイドラインで使用 |
| 他職種連携 | 自分以外の専門職との関わり | 「他者とのつながり」強調 | 実務的な文脈で使用 |
多職種連携と他職種連携の違い
似た言葉に「多職種連携」や「他職種連携」があります。どちらも複数の専門職が関わる点では共通していますが、ニュアンスに微妙な違いがあります。
「多職種連携」は多様な専門職が関わり合い、情報共有や役割分担を行うことを強調しています。医師・看護師・介護職員・リハビリ職・ケアマネジャーなど、多岐にわたる職種が集まることで、利用者の生活全般を支援する仕組みを意味します。
一方、「他職種連携」は自分の職種以外の人との連携に焦点を当てた表現です。主語となる職種が自分自身であることを前提に、「他の専門職とどう関わるか」という視点から使われます。
「協働」と「連携」の使い分け
「協働」は共に働く姿勢を強調し、実際の共同作業や合意形成のプロセスを含んでいます。制度用語としても介護保険分野では「協働」が用いられることが多く、チームとしての実践的な協力関係を示しています。
一方で「連携」は情報の共有や役割分担を中心にした関係性を指すため、より広い概念として用いられます。現場では両者が混在して使われていますが、制度的には「協働」が重視されている点を理解しておくと、用語の違いに迷わされずに済みます。
多職種協働の例
厚生労働省などの制度上の書き方では、以下のように多職種協働が使われます。
例えば、介護保険の個別機能訓練加算の実際の業務を示した文書では「多職種協働で個別機能訓練計画を作成する」と事務処理手順上行うこととして示されている場合には、一つの職種の人が単独で作成をするのではなく、多様な専門職が関わり合い、情報共有や役割分担を行うことが求められており、この場合であれば計画作成にあたって他の職種からも意見を求めたり、計画上の役割を割り振ったりしておかないとならないということになります。
把握した利用者のニーズ・日常生活や社会生活等における役割及び心身の状態に応じ、機能訓練指導員等が多職種協働で個別機能訓練計画を作成する。その際、必要に応じ各事業所に配置する機能訓練指導員等以外の職種(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科衛生士、管理栄養士等)からも助言を受けることが望ましい。
引用:リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について
一方で、望ましいと書かれていることについては、その表現通りできればやった方が良いという内容なので仮にやっていなかったとしても、強く指摘されたり業務を怠っていると言われるほどのことではないという意味で使われます。
参考:2024年~ 通所介護の「個別機能訓練加算」算定要件(機能訓練指導員ネットワーク)
まとめ
介護・医療・福祉の現場で用いられる「多職種協働」「多職種連携」「他職種連携」は、一見似ていますが意味合いや使われ方に違いがあります。制度的には「協働」が重視され、共に働く姿勢が求められています。現場では「連携」も頻繁に使われますが、単なる役割分担にとどまらず、利用者の生活全体を支える協働の意識が不可欠です。
介護保険の制度上は、チームでケアすることが重視されていることから、制度上の表現として使われるのは「多職種協働」が多い印象です。このような表現をされている業務がある場合には、1人で完結させたという状態にならないように、複数の職種が関わって話し合ったり、カンファレンスをしたことなどをしっかりと記録にも残しておく方が良いでしょう。
これらの違いを理解しておくことで、実際のチームケアや会議の場での言葉の重みが変わり、より質の高い支援へとつながります。
