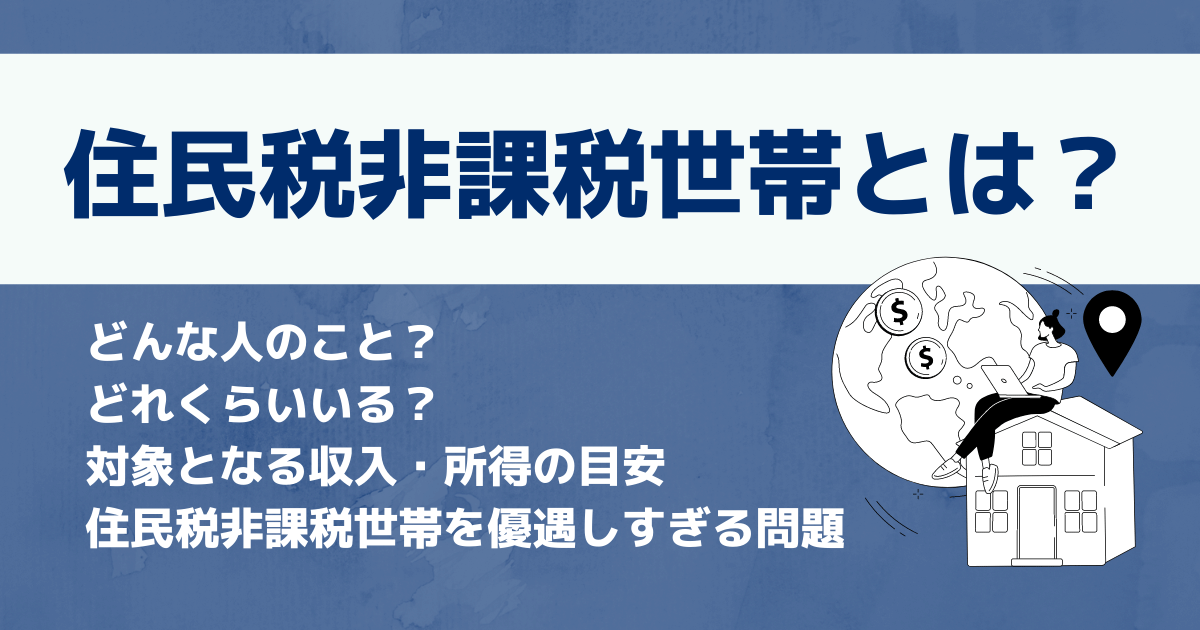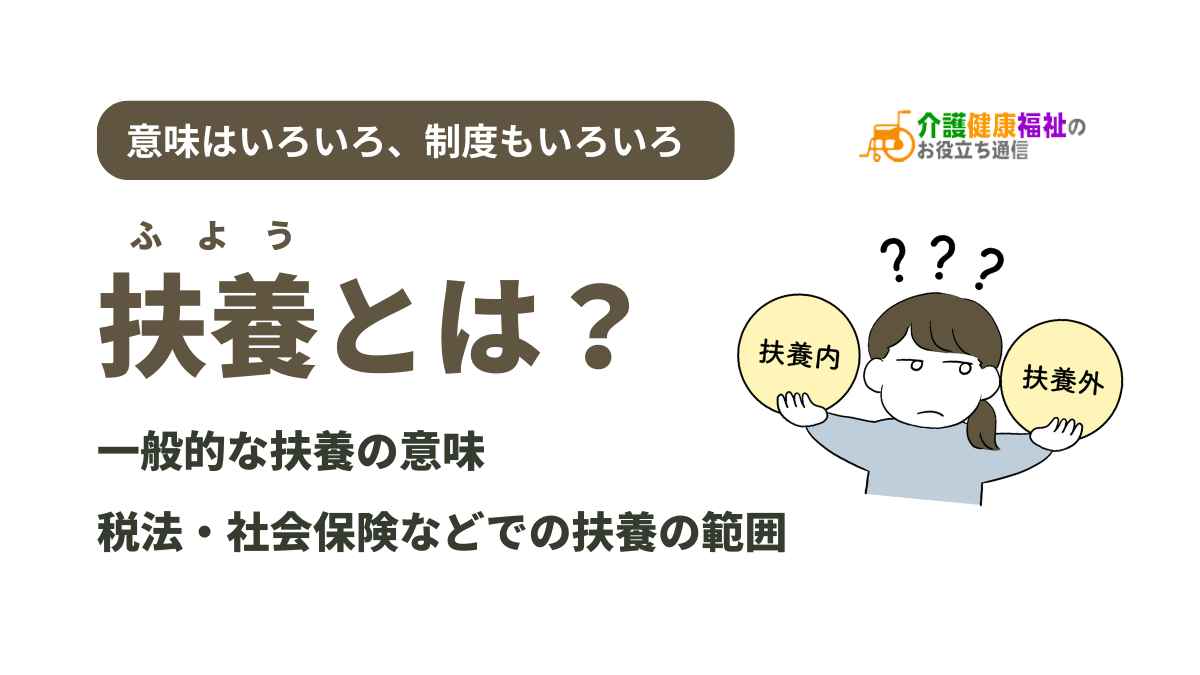
「扶養」という言葉は一つでも、税法と社会保険で意味も効果も異なります。年末調整の時期になると、配偶者控除や扶養控除、いわゆる年収の壁と健康保険・厚生年金の被扶養者認定が頭の中で混ざりやすく、何を基準に判断すればよいのか迷いやすいものです。
この記事では、まず日常語としての扶養の意味を整理し、そのうえで税法上の扶養(各種控除の要件と影響)と社会保険の扶養(被扶養者の認定基準と手続き)の違いを最新制度に沿ってわかりやすく解説します。さらに「扶養から外れる」とは具体的に何が起きるのか、家計や働き方に与えるメリット・デメリットを表で示し、年末調整や就労計画の意思決定に役立つ視点を提供します。
このページの目次
「扶養」の意味、なぜ扶養が分かりにくいのか
「扶養」は本来、家族の生活を支えることを意味しますが、制度の世界では文脈によって指す内容が変わります。税法で言う「扶養」と、健康保険や厚生年金の「被扶養者」は定義も効果も別物です。年末調整や「年収の壁」を調べるほど混乱しやすい用語だからこそ、言葉の意味と最新の数値基準を横並びで確認しておくことが大切です。
一般・税法・社会保険、扶養の3つの顔
日常語としての扶養は、家族の生活費を負担したり暮らしを支えたりする広い概念です。
税法上の扶養は、一定の要件を満たす親族等について所得控除(配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除・特定親族特別控除など)が受けられる仕組みを指します。
社会保険上の扶養は、健康保険や厚生年金の制度で「被扶養者」に認定されることを指し、保険料負担や給付の取り扱いに直結します。これらは重なることもありますが、同じではありません。
税法上の扶養、基礎控除・給与所得控除の改正と「123万円の壁」「160万円の壁」
160万円の壁
2025年分(令和7年分)から、所得税の基礎控除と給与所得控除が見直されました。基礎控除は所得水準に応じて段階的に63万~95万円、給与所得控除の最低保障額は65万円となりました。これにより、給与収入だけの方が「そもそも所得税がかからない」年収の目安は最大で160万円まで引き上がっています(所得により段階差があります)。
123万円の壁
同時に、配偶者や親族を「税法上の扶養」に含められるかどうかの判定に使う合計所得金額の要件も10万円引き上げられ、給与収入ベースの目安は103万円→123万円に見直されています。実務では「配偶者控除・扶養控除判定の目安が123万円」と捉えると整理しやすくなりました。
さらに、19歳以上23歳未満の大学生年代を支える新制度として「特定親族特別控除」が創設され、当該年代の親族の年収が一定範囲内であれば控除額が段階的に維持される仕組みになりました。
税法上の主な控除(2025年分)
| 区分 | 要旨(概要) |
|---|---|
| 基礎控除 | 所得に応じて63万~95万円に拡充。 |
| 扶養控除・配偶者控除 | 対象者の合計所得要件が引き上げられ、給与収入目安は123万円で判定に。 |
| 特定親族特別控除 | 19~22歳の親族等について、一定の年収帯で控除が段階的に維持される。 |
※具体の金額帯や速算表は国税庁「年末調整のしかた」等の資料で必ず確認してください。
社会保険の「扶養(被扶養者)」、106万円・130万円の壁と2024~2025年の拡大・緩和
社会保険では、被保険者に生計維持される一定の親族等が「被扶養者」に認定されると、自ら保険料を負担せず健康保険に加入でき、国民年金では第3号被保険者となる扱いが可能です。収入が増えると加入義務が生じたり、被扶養者から外れたりする分岐があり、これが「年収の壁」と呼ばれます。
106万円の壁
まず、106万円の壁は「短時間労働者でも、週20時間以上かつ所定の要件を満たすと、本人が健康保険・厚生年金に加入する」分岐を指します。2024年10月からは、対象企業の規模が従業員数51人以上へ拡大され、該当者は加入が必要になりました。
130万円の壁
一方、130万円の壁は「被扶養者として認定される年収の上限」の目安です。収入が継続的に130万円以上見込まれると、被扶養者から外れ、本人が社会保険に加入または国保・国民年金に切り替える必要が生じます。政府は一時的な超過で扶養から外れないよう、事業主証明による当面の緩和策も示しています。
さらに2025年10月からは、19~22歳(19歳以上23歳未満)の親族について、健康保険の被扶養者認定の年収基準が130万円未満→150万円未満へ一部緩和される見直しが始まります(配偶者は対象外)。
住民税と扶養、扶養控除の金額差と非課税判定のしくみ
住民税でも「扶養」の概念は重要で、まず所得控除としての扶養控除があり、次に非課税判定(均等割・所得割)で扶養親族の有無と人数が基準額に反映されます。税法上の扶養控除額は所得税と住民税で金額が異なり、住民税では一般扶養親族が33万円、特定扶養親族(19〜22歳)が45万円、老人扶養親族が38万円、同居老親等が45万円という水準が各自治体の案内で示されています。したがって、同じ親族を扶養していても、所得税と住民税で控除額は一致しない点に注意が必要です。
あわせて、住民税には非課税となる収入の目安があり、前年の合計所得金額が一定以下であれば均等割や所得割がかからない取り扱いがあります。この判定式は自治体条例に基づきますが、代表的には「35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)に加算額を足す」という枠組みで、扶養親族が多いほど非課税限度額が上がる構造です。
例えば、同一生計配偶者や扶養親族がいない単身者は合計所得金額45万円以下で非課税、扶養人数が1人ならおおむね112万円以下で所得割が非課税という目安を示す自治体の早見表もあります(給与収入のみに換算した目安も公表されています)。この仕組みにより、16歳未満の子は扶養控除の対象にはならないものの、非課税判定では「扶養人数」に数えられるため、課税の有無に間接的な影響を与えることがあります。
扶養人数と住民税所得割が非課税になる目安のイメージ
| 扶養人数 | 合計所得金額の目安(所得割が非課税になる上限) | 給与収入のみの参考目安 |
|---|---|---|
| 0人 | 45万円以下 | 100万円以下 |
| 1人 | 112万円前後以下 | 170万円前後以下 |
| 2人 | 147万円前後以下 | 221万円前後以下 |
住民税でも「誰を何人扶養しているか」は控除額にも非課税判定にも影響します。年末調整や就労時間の調整を検討するときは、所得税だけでなく住民税の扶養控除額と非課税基準も並べて確認すると、手取りの見通しがぶれにくくなります。
税と社会保険で違う、「扶養から外れる」とは何が起きるのか
税法で「扶養から外れる」とは、配偶者控除や扶養控除、特定親族特別控除などの適用対象から外れることを意味します。控除がなくなる分、扶養している側の税負担が増える可能性があります。社会保険で「扶養から外れる」とは、健康保険の被扶養者認定が外れることを意味します。本人は勤務先で健康保険・厚生年金に加入するか、勤務先要件を満たさない場合は国民健康保険と国民年金第1号へ切り替えることになります。結果として、本人に保険料の自己負担が発生します。
| 項目 | 税法上の扶養から外れる | 社会保険の扶養から外れる |
|---|---|---|
| 主な効果 | 扶養者側の所得控除が受けられない(税負担が相対的に増える) | 本人に保険料負担が発生(職場加入または国保・国年へ切替) |
| 代表的な分岐 | 給与収入目安123万円超などで判定が変わる | 年収130万円以上見込み、等。19~22歳は2025/10から150万円未満に緩和(配偶者除く) |
| 相談先 | 会社の年末調整担当・税理士・国税庁資料 | 会社の社保担当・年金事務所・健康保険組合 |
扶養から外れるを理解するポイント
家族が「税法では扶養のままでも、社会保険は扶養から外れる」ケースがあり得ます。
たとえば短時間の就労が週20時間を超え、かつ企業規模要件に該当すると、本人は社会保険に加入しつつ、税法上の控除は一定範囲で維持されることがあります。逆に、税法上は123万円を超えて控除が縮小・消滅しても、社会保険では130万円未満(または19~22歳で150万円未満)を維持しているあいだは被扶養者のままという場面もあります。制度がずれると家計も変わりますので、控除額・保険料・手取りを年単位で試算してから就労時間やシフトを調整することをおすすめします。
言葉を分けて考えれば迷わなくなります
扶養という言葉は一つでも、税法と社会保険では定義も効果も違います。2025年分からは基礎控除と給与所得控除が拡充され、「税の壁」は見直されました。税法上は123万円目安での判定が増え、大学生年代には新たな特定親族特別控除が導入されています。社会保険では、106万円の壁の対象拡大や130万円の壁の当面の緩和、さらに若年層の150万円基準の導入など、連動する動きが続いています。まずは言葉を分け、表で見比べ、最新の公的資料で金額と条件を確認することが、年末調整や就労計画の混乱を避ける近道です。