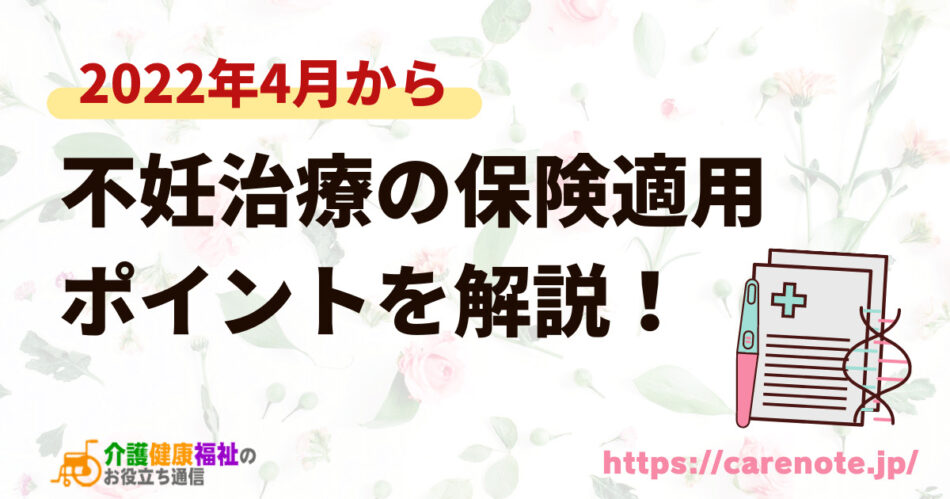
2022年4月から不妊治療である生殖補助医療(体外受精、顕微授精、男性不妊の手術)も保険適用が拡大されることが正式に決まりました。保険適用となる 不妊治療には年齢や回数に制限がありますが、高額な不妊治療費でも保険適用で3割負担で済むようになり、医療費控除の対象にもなります。厚生労働省のQ&Aなども引用し、ポイントをまとめていきます。
このページの目次
不妊の原因
不妊の原因は、診察所見、精子の所見、画像検査や血液検査等を用いて診断されますが、以下の3つに大別されます。
- 男性不妊
- 女性不妊
- 原因が分からない機能性不妊
広告
不妊治療とは
男性側に原因
男性側に原因があるケースとしては、精管閉塞、先天性の形態異常、逆行性射精、造精機能障害などがあり、手術療法や薬物療法が行われます。
女性側に原因
女性側に原因があるケースとしては、子宮奇形、感染症による卵管の癒着、子宮内膜症による癒着、ホルモンの異常による排卵障害や無月経などがあり、手術療法や薬物療法が行われます。
原因不明の不妊や治療が奏功しないもの【2022年4月から新たに保険適用】
一般不妊治療
タイミング法
タイミング法とは、排卵のタイミングに合わせて性交を行うよう指導します。
人工授精
人工授精とは、精液を注入器で直接子宮に注入し、妊娠を図る技術です。主に、夫側の精液の異常、性交障害等の場合に用いられます。
生殖補助医療
体外受精
体外受精とは、精子と卵子を採取した上で体外で受精させ(シャーレ上で受精を促すなど)、子宮に戻して妊娠を図る技術です。
顕微授精
顕微授精とは、体外受精のうち、卵子に注射針等で精子を注入するなど人工的な方法で受精させる技術です。
男性不妊の手術
男性不妊の手術とは、射精が困難な場合等に、手術用顕微鏡を用いて精巣内より精子を回収する技術(精巣内精子採取術(TESE))等です。
広告
不妊治療の保険適用条件
2022年4月より、「一般不妊治療」のタイミング法・人工授精、「生殖補助医療」の体外受精、顕微授精、男性不妊の手術が保険適用されることとなりました。
広告
保険適用外の不妊治療
第三者の精子・卵子等を用いた生殖補助医療
第三者の精子提供による人工授精(AID)、第三者の卵子・胚提供、代理懐胎については、「生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律」(令和3年3月11日施行)の附則第3条に基づき、配偶子又は胚の提供及びあっせんに関する規制等の在り方等について国会において議論がなされているところであるため、2022年4月現在は保険適用の対象外です。
広告
不妊治療の助成金
生殖補助医療(体外受精、顕微授精、男性不妊の手術)は、2022年3月までは「特定不妊治療」と呼ばれ、助成金の対象でした。2022年4月からは「生殖補助医療」として整理され、保険適用の不妊治療法となりました。
広告
不妊治療の年齢制限・回数制限
不妊治療の年齢制限
治療開始時において女性の年齢が43歳未満であること
年齢・回数の要件(体外受精)は助成金と同じで
不妊治療の回数制限
初めての治療開始時点の女性の年齢40歳未満 通算6回まで(1子ごとに)
初めての治療開始時点の女性の年齢40歳以上43歳未満 通算3回まで(1子ごとに)
※ 助成金の支給回数は、回数の計算に含めません。
広告
不妊治療と医療費控除
国税庁のホームページによると、不妊症の治療費・人工授精の費用は「医師による診療等の対価として支払われる不妊症の治療費及び人工授精の費用は、医療費控除の対象となります。」と示されいてます。
不妊症の治療費・人工授精の費用
【照会要旨】
不妊症の治療費や人工授精の費用は、医療費控除の対象になりますか。【回答要旨】
医師による診療等の対価として支払われる不妊症の治療費及び人工授精の費用は、医療費控除の対象となります。【関係法令通達】
所得税法施行令第207条
広告
不妊治療と保険適用のQ&A
厚生労働省作成「令和4年4月から、不妊治療が保険適用されます(リーフレット)」から、Q&Aを抜粋しました。
ケアマネジャーの転職は、ケアマネ専門の転職サイトを利用しよう
ケアマネジャーの転職はケアマネ専門の転職サイトの利用が安心です。自分で求人を探したり、人づてに紹介してもらったりする場合、本心では希望している条件をいろいろ我慢してしまいがちになります。転職サイトを挟むことで、希望に合う職場を見つけてもらい、見学・面接対策・条件調整なども行ってもらえるので、希望理由や面接対策で悩んだりすることも減ります。新人ケアマネも、ベテランのケアマネも専門の転職サイトの方がケアマネの求人情報を多く持っています。
居宅介護支援事業所では人手不足状態、ケアマネージャー、主任ケアマネージャー資格を有する人の求人が増えています。多くの転職サイトは介護の仕事のおまけのような感じでケアマネの転職支援をしていますが、ケア求人PECORIだけはケアマネ専門なので、登録して電話面談するときにもケアマネとしての状況や今後の働き方、賃金の相場などを相談しやすいです。
「ケア求人PECOLI」は、ケアマネージャー専門の転職サイトという大変珍しいサービスで、ケアマネに特化して全国の転職支援を行っています。他の転職サイトに登録しても、よい求人が見つからなかったり、電話の人と話が合わなかったりしてうまくいかなかったケアマネも、すぐ登録できるので一度登録してピッタリな求人・転職先の紹介を受けてみましょう。(運営:株式会社PECORI 職業紹介許可番号(厚生労働大臣認可):13-ユ-308091)
